まちを知る
-

季節限定の和菓子から「猫神さま」まで。長岡の風土と文化に息づくニャンコたちの姿を求めて
突然ですが、2月22日は何の日でしょう? そう、「ニャンニャンニャン」、つまり猫の日です(当然、これは日本だけの語呂合わせ。世界猫の日は8月8日とされています)。というわけで、今回はキュートな姿でわたしたちを笑顔にしてしまう「猫」にまつわる長岡のスポットや商品を一挙ご紹介します。猫と暮らす方も、そうでない方も、思わずほっこりしてしまう長岡の猫スポット・アイテムをぜひチェックください。 &nb
-
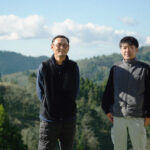
小さくても、僕らの世代でやれることから少しずつ。「小さな山古志楽舎」がつなぐ、地域コミュニティの灯
JR長岡駅から車でおよそ40分、長岡市の南東部に位置する、豊かな自然の残る中山間地域の山古志。2004年の中越地震にて大きな被害を受け、長岡市内に(当時は山古志村であり、長岡市とは別の自治体)全村避難を行った際の仮設住宅の住み分けでも山古志のコミュニティを崩さないよう住民同士でまとまり、小中学校も市内の学校に間借りする形で再開するなど、地域のつながりを大切にしてきたエリアでもあります。 昭和
-

雪国初心者必見!雪かき伝道士が教える「大雪の前後にやるべきこと」※大雪防災情報・公的支援リストつき
2021/3/2 2020年の暮れから2021年の初頭にかけて、記録的な大雪に驚いた人は多いだろう。豪雪地帯である新潟県長岡市の中でも雪深い山古志種苧原(やまこしたねすはら)地区では、最大積雪量317センチを観測。とくに年末や成人の日前後の大雪は交通機関のトラブルを生み、たくさんの人の日常生活が混乱した。 筆者は昨年秋に東京から引っ越し、今年新潟で初めての冬を迎えているが、「当たり年に来た
ひとを知る
-

【長岡蔵人めぐり 第10回】「速醸造り」発祥の蔵! ブレない酒造りで地域に福を招くお福酒造
日本屈指の酒どころ、長岡市内の16蔵をめぐるこの企画。今回お邪魔したのは、東山山系の麓、豪雪地帯の横枕町にあるお福酒造です。明治時代に「速醸造り」と言われる醸造技術を開発し、日本酒の安定量産を可能にした伝説の人物、岸五郎が設立した蔵でもあります。日本酒醸造の近代化を進めたと言っても過言ではないお福酒造は、今どんなお酒を作っているのでしょうか。そして、時代の変遷に合わせて、どのように酒造りを変化させ
-

米国人女性と農家のかあちゃん。二人が「食」から考える“発酵的な暮らし”とは
2019/10/10 「発酵・醸造のまち」を掲げる、新潟県の長岡市。全国有数の米どころである新潟県において16もの酒蔵を有し、江戸時代から栄える摂田屋エリアでは味噌蔵・醤油蔵・酒蔵などが密集。大学や企業の発酵研究機関も多数あり、“発酵スポット”として注目されています。全国的に発酵への注目は続いていますが、長岡では食品以外にもスポットを当てた取り組みをしているのが特徴。「暮らしや生き方も発酵させて
-

東京より愛を込めて。東洋一の闘牛ラバーが語る「越後山古志の角突き」の魅力とは
2019/8/21 「『ドシーン!』ってね、そりゃもうすごい迫力で。とにかく圧巻なんですよ!」 新宿と渋谷からほど近い人気の住宅街・幡ヶ谷。ここで34年の長きにわたり地元民に愛される精肉店「ミートショップ・グルメナカムラ」には、前沢牛をはじめとする目利きの効いた精肉や手作り惣菜が並ぶ。この店の社長・中村勇士郎さんは、新潟県長岡市の伝統行事「越後山古志の角突き」の筋金入りのファンである。


