演歌・歌謡曲界の新星、中澤卓也24歳。故郷・長岡への思いと歌にかける夢を訊いた

歌手、中澤卓也(24歳)。新潟県長岡市に生まれ、2017年1月「青いダイヤモンド」でデビュー後、演歌・歌謡曲ジャンルで数々の新人賞を受賞した実力派だ。ミラクル・ボイスと称される伸びやかな声、端正なルックスと丁寧な人柄で女性からの人気が高く、地元新潟県でのコンサートはチケットがとれないと嘆くファンも多い。
ストリートファッションを愛する、現代の若者。彼は、いつどのように演歌・歌謡曲を自分の道と定めたのだろう。長岡で生まれた彼が、何を見て聞いて育ち、今、どのような歌を私たちに届けようとしているのか、歌手、中澤卓也の今までとこれからに迫った。

https://www.nakazawatakuya.com/
レーシングドライバーを
目指していた少年時代

――今日はテレビの収録やコンサートの準備などでお忙しいなか、お時間をいただきありがとうございます。早速なのですが、中澤卓也さんが歌手を目指すまでのいきさつをお聞きしたいと思います。中澤さんは長岡のご出身とお聞きしました。どんな幼少期を過ごされたのでしょうか?
実家が信濃川にかかる蔵王橋のふもとだったので、近くに土手があったんです。少年時代はその土手を父とサイクリングしたりしていました。だから長岡の四季を感じる景色とか風にふれることはすごく多かったですね。
――そのころから歌に興味をお持ちだったんでしょうか。
いえ、僕は小学校3年からずっとレーシングドライバーを目指していました。レーシングカートというプロのレーシングドライバーが登竜門にしているカテゴリーでレースをしていまして、地元のスポーツランド長岡というサーキット場をホームコースにしていました。高校もレーシングドライバーになる夢をかなえるために開志学園高等学校に新設されたばかりのモータースポーツ科に進学したんです。
――大きな夢にむかってかなり本格的に行動していたんですね。
レースは高校1年まで続けていました。でも、モータースポーツというのはとてもお金がかかるスポーツで、資金難で続けられなくなってやめてしまったんです。自分で真剣にレースでご飯を食べていこうと思っていたので、心にぽっかり穴があいてしまって。どん底だったんですよ。そのあとは、一年間どこの科にも所属しない状況が続いていました。ありがたいことに、先生がそれを許してくれて。目標を失ってつらいときだろうから、しばらく考える時間をもってみたら、って。単位制の高校だったので、授業のないときはひたすらバイトをしているという日々でした。
そんなときに、新潟県の津南町に住む祖母が「長岡でNHKのど自慢があるよ」って僕に教えてくれたんです。祖母も僕がレースをやめて悶々としていることを心配してくれていたんですよね。それで「気晴らしに出てみたら」と軽い感じで言われたので、じゃあ、軽い気持ちで応募してみようかな、と一枚だけハガキを書いて投函したんです。歌は小さいころから好きだったし、コブクロ、平井堅さん、森山直太朗さんとか、ポップスのバラードをずっと聴いて育ってきました。のど自慢にも森山直太朗さんの『さくら(独唱)』で応募したんです。そうしたら、予選会に来てくださいという通知が来て。高校にはボーカル科もあったので、そこに編入することにしました。そのときは歌手になろうとは考えていなくて、自分のなかで何かを見つけなくてはいけない、との思いからでした。

一枚の応募ハガキが変えた運命
――ご家族の思いに後押しされるように、NHKのど自慢に応募し、高校でもボーカルを学ぶ道を選び、少しずつ歌への道が開けてきたわけですね。
高校2年の3月末、予選会に出て、本選出場者に残り、本選で今週のチャンピオンになって――。あとから知ったことですが、『のど自慢』って応募者もとても多いですし、一人で何十通応募しても予選に出られない人もいるそうです。そんななかで、自分はたった一枚しか書いていない。その一枚が全部のきっかけになったんです。
➣当時、高校生の中澤卓也さんがのど自慢でチャンピオンになったときの貴重な画像はこちら

『のど自慢』のあと、たくさんの友達から連絡をもらって元気づけられました。レースをやめてどん底だったけれど、また新しい目標を作ろう、車関係の仕事とか、レースの舞台を裏から支える人間になるとか考えてみよう、と前向きになれました。チャンピオンになった、それだけでもう十分だったんですよ。そこへレコード会社から実家に電話がかかってきたんです。その日、僕は友達と出かけていたのですが、珍しく母から携帯に電話が来て、「今、日本クラウンというレコード会社からうちに電話があって、のど自慢の放送を見て歌を聞いてすごくいいと思ったので、うちで歌手になりませんかって話がきているけれど」と。驚いて、友達に「俺、今日は帰るわ」と帰宅して。放送から一週間もたたないくらいの頃でした。
思いがけない
演歌・歌謡曲への誘い

――レコード会社からのスカウトという、中澤さんにとって人生の大転換期がくるわけですね。
『のど自慢』から約一カ月後のゴールデンウイークに日本クラウンの方が長岡に来てくださって、長岡駅ビルの喫茶店でお会いしました。そのとき初めて「演歌・歌謡曲を歌いませんか」と言われたんです。でも僕はそれまでポップスが好きで、演歌・歌謡曲はまったく聞いたことがありませんでした。正直、自分が歌いたい、歌いたくないという以前に、自分が知らないジャンルだし、聞いたことないし、知識がゼロなんで果たして僕に歌えるんだろうかという不安がすごくあって。申し訳なかったのですが、すぐにお返事はできませんでした。
帰宅して家族と話をしました。そこで母が言ってくれた言葉があるのですが「歌手になりたくてなれない人もいるなかで、レースという一つの夢を突き詰めてきてそれを諦めたあなたに、こんな一年足らずでものすごいチャンスがあるというのはなかなかない。レコード会社の人が歌手になりませんか、と言ってくださるんだったら、できるできないは関係なく、やれるだけやってみたらどうなの」って。確かにそうだなと思って。起きてもいないことに不安になってもしょうがないし、今は身を委ねてみよう、と。
6月ごろには日本クラウンの本社に行ってレコード会社がどういうところなのか紹介してもらい、夏には作曲家の田尾将実先生に師事することになり、9月からレッスンが始まりました。演歌・歌謡曲のことも業界のことも先生に一から教えてもらうことになりました。『のど自慢』出場から数カ月で、あっという間、怒涛のようにガラッと生活が変わりました。
本当にいい歌は人の手を止める。
視野を開いた師匠の言葉

――プロの歌手になるためのレッスンが始まったわけですが、どんなレッスンだったのでしょう。
田尾先生に初めてお会いしたときに、ご自宅のピアノが置いてある仕事部屋に案内されました。先生がこのピアノを弾きながらマンツーマンでレッスンするんだろうな、と思っていたら、一枚CDを渡されて『この中に発声練習用の音源が入っているから、その音に合わせて見よう見まねでいいから発声をやってみてくれ』と言われ、先生はレッスン部屋から出ていってしまいました。先生が弾くピアノの音が入ってる10分尺くらいのCDです。その音に合わせて、「アーエーイーオーウー(音階で半音ずつ上がっていく)」とか「マママママママママ〜(ドレミファソファミレドの節で)」などの発声練習をするわけです。
その練習中、先生は全然部屋に入ってこないんですよ。想像とまったく違うレッスンで、自分の発声がいいのか悪いのかもわからない。わからないなりに、毎回2~3時間、ひたすらその発声練習だけをするんです。僕が練習している間、田尾先生は手料理を作ってくれるんですよ。すごく上手で本当に美味いんですけれど。発声のあとは、その手料理を一緒に食べて音楽について話をしたりとか、今トップで歌っている先輩方のライブの映像を見たり、洋楽のアーティストのコンサートの映像を見たりしながら音楽の勉強を1~2時間して、夜8時台とか終電の新幹線で新潟に帰るっていうのが続いたんです。
レッスンを続けて半年たったときに先生に「発声法がだんだんよくなってきたから歌を覚えてくれ」と言われて、最初の課題が、松山千春さんの『恋』と因幡晃さんの『わかって下さい』でした。その2曲をひたすら2~3時間ずっと歌い、そこでも先生が部屋に入ってくるわけでもなく、終わったら手料理を食べて帰るというのが続きました。
一年くらい続いたときに「卓也、なんで俺がレッスン部屋に行かないかわかるか」って言われました。ずっと聞きたかったことなので「わからないです、教えてください」と言ったら「歌は聴こうと思って聴くものじゃない。CDとかラジカセを目の前に用意して、よし、俺は今から歌を聴くんだ!って正座しては聴かないだろう。ラジオから聞こえてくる歌を、運転しながら、台所で何かしながら聴いたり、ウォークマンやスマホで歩きながら聴いたり、今、音楽は何かをしながら聴くものになっている。でも何かをしながらでも、本当にいい歌っていうのは、聴く人の手を止めるんだ」って言われたんですよ。確かに、僕もコブクロの音楽を聴いたとき、何かをしながら聴いていたはずなんですけれど、うわ、すごいな、この人たち!って衝撃を受けたんですよね。先生は続けて「だから、おまえが歌っている部屋に俺はあえて行かないんだ。お前の歌は聴いているけれど、聴きながらお前と食べる飯を作ったり、掃除機かけたり、洗濯物を干したりしている。だから俺の手を止める歌を歌えるようになれ」と言われて。本当におっしゃるとおりだなと思って、それで視野が開けたんです。このやり方で間違ってないんだな、先生に響く歌を歌えるようになりたいなって思うようになりました。レッスンのスタイルは今でもずっと同じで、たぶん一生このスタイルだと思います。新曲ができて、レッスンに行っても、先生は僕の歌う部屋には一切入ってこない、というスタイルが続いていくんだと思います。
――そうして先生は、何かをしながら、中澤さんの歌が、自分の手を止めるそのときを待っていらっしゃるんですね。
そうです。今だに手を止められてないんですけどね(笑)。
――中澤さんという原石をどう磨いていこうかという先生のお気持ちを思うと…すばらしいですね。
本当にいい先生に恵まれたなあ、と思っています。

歌って気づいた
演歌・歌謡曲の魅力
――演歌・歌謡曲はもともとは関心がなかったということでしたが、歌うことになって演歌・歌謡曲の魅力に気づいたエピソードはありますか?
そうですね。田尾先生から課題でいただく曲もあるんですが、自分でもいろいろ聴いてみようと思って、よく通販されているような懐かしの歌謡曲何枚組みたいなCDを買って、車の運転中にひたすらかけました。そのときに「氷雨」など、歌謡曲の名曲に出会って、今までポップスを聴いたときと違うしびれかたをしたんです。ポップスの場合は、体を動かさせてくれたりとか笑顔にさせてくれたり、元気にさせてくれたり、そういう作用を感じるんですけれど、演歌・歌謡曲を聞いたときに、よりそれが表面的ではなく、心をぐっとつかんで揺さぶられるような気が、僕はしたんですね。メロディーも聴きやすいですし、言葉もすごく考えられていて美しいですし。演歌・歌謡曲に対して違和感を何も僕は感じなかったんです。だからこそ、僕は今でも普通に歌えているんだと思うんです。
演歌・歌謡曲にはいろんな主人公が出てきます。女性なら、強い女性のパターンもあれば、弱い女性のパターンもあります。さみしさを全面に出しているのか、さみしさを隠すがごとく生きているのか、いろんな表情がそれぞれの歌にあるんですよ。それってポップスの歌にはあまりないところかもしれません。いろんな土地が舞台の歌もあります。新潟でいえば『新潟ブルース』(美川憲一)という歌があって僕もよく歌うんですけれど、それを九州や北海道で歌ったときに、同じ新潟の景色を少なくともお客さんと見ることができるわけですよね。その場所に行けなくても歌を通してお客さんと旅に出られるのが、演歌・歌謡曲の魅力かな、と思います。

心に宿している
故郷・長岡の風景

――歌手になってから中澤さんの目に、地元である、新潟や長岡の景色はどのように映るのでしょう。
デビュー前は、当たり前に自分のそばにある景色だったんですよね。でも上京してデビューして新潟を離れて、また、新潟でお仕事をいただくようになって、毎度思うのは、ほっとするな、ということなんです。あったかいんですよね。それは自分の育った土地だからかもしれないんですけれど、長岡の景色や空気、またはにおいだったりとか、いろんな要素があるんです。すごくいい町だな、と思います。


――長岡で、特にこの景色を見るとほっとする、という場所はありますか?
信濃川の土手から見る景色や、あと、天気のいい日に自宅から見る夕焼けもきれいなんですよね。あとマニアックなんですけど、国道8号線(長岡バイパス)を柏崎方面から長岡市街地に向かって車で走るときに、国営越後丘陵公園の側を通り過ぎて、上除から日越にかけて下り坂があるじゃないですか。あの下る瞬間に見えるあの長岡の景色が、すごく好きなんですよ。特に夜です。すごくきれいなんです。
もうひとつ、車で走っていて好きな景色があって、長岡商業高校の前を通って栃尾に抜けていく道(国道351号線)がありますよね。あの道のトンネルに入る前のところなのですが、あの山を上っていった帰り、トンネルから出てきて下りてきて、カーブを曲がったとき視界が全部開ける瞬間があるんですよ。あそこは夕暮れ時もきれいです。田畑があって、川があって、向こう側に日赤病院も見えて、丘陵公園側の山も見える。すごいマニアックですね(笑)。伝わります?
――伝わります! わかります! 少なくとも長岡市で車によく乗る方なら、ああ、あの風景か、とわかるのではないでしょうか。長岡市街地をはさんで、西側と東側、それぞれから長岡が一瞬一望できる場所ですよね。気持ちも開けるような気がしますよね。
そうなんですよ。
――なんだか中澤さんに一気に親近感がわいてきました。

(中澤さん、爆笑)
――こうした地元の景色が中澤さんの原風景になっているんですね。歌うときに長岡の風景を思い浮かべたりするのでしょうか。
演歌・歌謡曲って歌のなかに景色がすごく出てきたりするので、歌いながら長岡の景色をあてはめていることはすごく多いんですよ。デビューシングル『青いダイヤモンド』のカップリング曲『黄昏に』という歌では、信濃川の土手を夕暮れ時に歩いている景色をあてはめて歌っています。
いろんな歌い手さんがいると思うんですが、主人公がいて、その心情を想像して自分の中に取り込むという人が大半だと思うんです。でも僕の場合はちょっと違っていて。僕は歌うとき、主人公が体験している物語を第三者側から見るようにしているんですよ。登場人物たちに芽生えた感情や、彼らが見ている景色など、自分の中で物語を作るわけです。その登場人物たちがいる景色が、どこかで必ず、長岡の景色なんですよね。自分のなかで歌詞をかみくだいて出てきたストーリーを歌うというパターンです。だから地元、長岡というのが自分のなかでより重要なんです。
――中澤さんの歌の歌詞をあらためて読みながら、この歌詞を自分なら長岡のどの景色にあてはめよう、と考えてみたくなりました。
夢はレコ大、紅白歌合戦のステージ
――それでは最後に、中澤さんの今後の目標についてお聞かせいただけますか。
やっぱり年末の大舞台、レコード大賞とか紅白歌合戦のステージを目標にしています。自分の歌手としてのステイタスというより、それも大事なことではありますが、応援してくださる皆さんの力で僕がレコード大賞や紅白歌合戦のステージに立てるようになりました、って見せてあげることが、中澤卓也を応援したいとCDを買ってくださる全国の皆さんへの一番の恩返しになるんじゃないかと思うんです。なので僕はまずそこを一番の第一目標にしたいな、と思っていて。演歌・歌謡曲を聞いたことがまったくなかった自分が、今こうしてご縁をいただいて歌っている。それには必ず意味があると思っています。また、ポップスも歌わないわけではありません。僕のテーマはジャンルレス。音楽ジャンルの架け橋となるような歌い手になりたいので、老若男女どの世代の方がコンサートに来てくださっても、一つ屋根の下でみんなで同じ中澤卓也という人間を楽しんでもらえる、そんなふうになってくれたら嬉しいなと。武道館のような大きな舞台にも立ちたいですし、野外コンサートとかもやってみたいですし、いろんなことに挑戦してみたいですね。
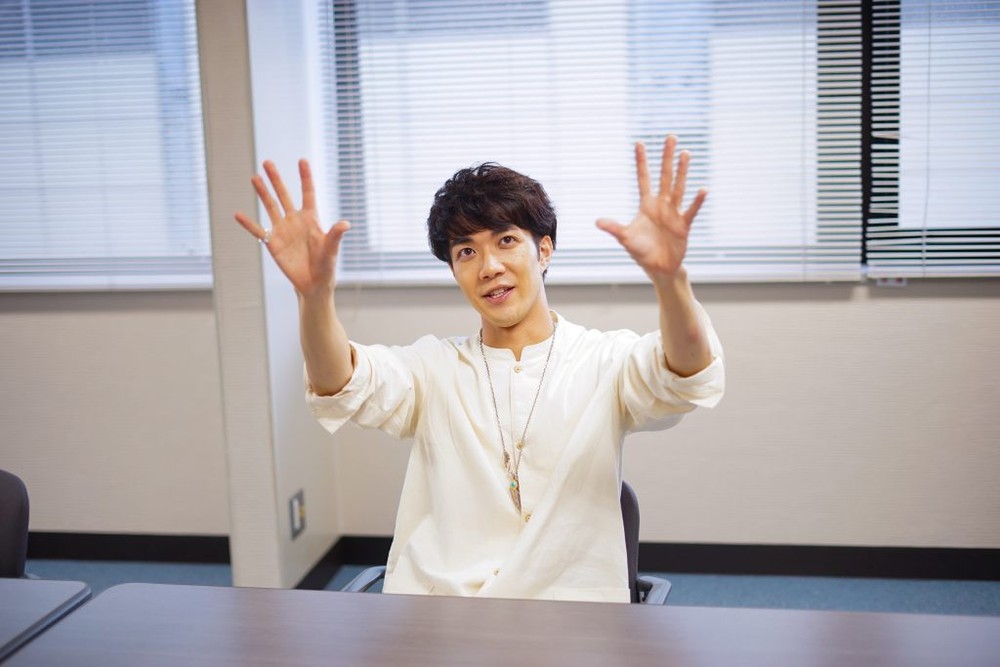

――2019年9月の日本青年館のコンサートでは、ご自身の持ち歌だけでなく、野口五郎さん、森昌子さんなど演歌・歌謡曲の名曲から、さらにDEEN、kinki kidsなど、ロックバンドやアイドルの歌まで、驚くほどさまざまなジャンルの歌をカバーされていますね。実際に行かれた方とお話したのですが「いろんな歌を歌ってくださって本当に素晴らしかったの!」と熱く語ってくださって。70代のその方がたくさんの時代を超える名曲に出会われたんだな、その機会を中澤さんが作ってくださっているんだな、と思いました。
そうですね。僕自身が演歌・歌謡曲というジャンルと出会ってすごく変わりましたし、すごくいいジャンルに出会えたなあという感覚がすごくあるので、この同じ感覚になれる人っていっぱいいると思うんですよね。若い人たちは演歌・歌謡曲を聴かないし、「おじいちゃんおばあちゃんが聴く音楽でしょ」っていうイメージがあると思います。そのイメージを正直、僕も持っていたんですよね。で、それがすごく必要のないことだな、と自分の体を通して感じたので、それを若い人たちにも届けていきたいですし、逆に「俺は演歌・歌謡曲しか聴かないんだ」という人に、いや、ポップスにもこういういいバラードがあるんですよ、と聞かせてあげれば新しい出会いになるかもしれない。だから音楽ジャンルをつないでいけるようなアーティストになりたいな、という思いがすごく強いです。
――「ジャンルの架け橋」となる中澤さんのご活躍を期待しております。すばらしいお話を聞かせていただきましてありがとうございました。


まなざしの向こうにある未来図

インタビュー中に、エンターテインメントに大切なものは?と聞くと、「いかに自分が見てる側になれるかだと思います。自分の伝えたい楽しさがステージの向こうに何パーセント伝わっているのか、足りないところは何なのか考えること」と彼は答えてくれた。デビューから3年、活躍の幅が広がりつつある24歳の青年の、落ち着いた答えに驚かされた。中澤卓也の強みは、全体をとらえようと俯瞰する視線にあるのかもしれない。それは歌詞の世界を第三者視点で読み込む姿勢ともつながっている。地元で愛する景色が、坂道を下る一瞬に開ける、市街を一望する風景だというのも彼らしい。自身の立ち位置をマッピングするかのような彼の視点は、もしかすると、速さと精度を競ったレーサーを目指していた時代に培ったものなのかもしれない。挫折を糧に、ミラクル・ボイスを武器に、真摯に挑戦を続ける中澤卓也。その視界はどこまで広がり続けるのだろう。彼がこの先、どんな歌を聴かせてくれるのか、どんな未来図を描いているのか。歌手・中澤卓也の活躍から目が離せない。
Text: Chiharu Kawauchi
photo: Iketo Hirokuni
















![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)

