【長岡蔵人めぐり 第12回】「きれいな酒」の秘密は米の扱いにあり!伝統を守りつなぐ諸橋酒造

酒どころ新潟県長岡市の16蔵を巡る本企画。今回訪れたのは、山間地・栃尾地域にある「諸橋酒造」です。170年以上の伝統を誇る老舗酒造が、その酒質を変化させないために努めていることとは何でしょうか? 伝統を守り続けるだけでなく、新たな可能性を追求するための挑戦についても伺いました。
おいしい水に恵まれた
山間地で醸す伝統の酒

例年、降雪量3メートルを超える栃尾地域。澄んだ冬の空気が気持ち良く、辺りは凛とした空気に包まれています。

風格ある佇まいの諸橋酒造。建物の手前はショップと事務所、奥が蔵となっています。

ほの暗い蔵に規則正しく大型タンクが並びます。

10年前に建て替えた麹室は、清潔性を考慮してステンレス壁に。ひとりでに湿度を調整してくれる木壁と異なり乾燥しやすいため、はじめのうちは苦労したのだとか。

吟醸酒造りに使用した絞り袋。ひと仕事終えた道具たちが、日の光を浴びながら気持ちよさそうに干されている姿にほっこりします。

百何十年もの時を蔵人たちと共に歩んできた蔵は、どこかおごそかな空気が漂っています。

「酒母(しゅぼ)」と呼ばれる液体。蒸米や麹、水を合わせて酵母を培養したもので、10日間経ったものはぷくぷくと発酵してアルコールの芳醇な香りを放っています。
目指すのは料理に寄り添う
「黒子」のような酒

「越乃景虎」定番の4種。(左から)「龍」は日常の晩酌で楽しめる普通酒。「超辛口 本醸造」は日本酒度12度ながら辛みを感じすぎない心地よい飲み口。「超辛口」は辛口好きにおすすめのバランス感が秀逸な逸品。「名水仕込み 特別純米酒」は地元の名水「杜々の森湧水」を使用した澄んだ口当たりを楽しめます。
端麗辛口ながら辛みを感じすぎず、すっきりした後味が特徴。爽快なキレの“きれいなお酒”は、全国の日本酒ファンに愛されています。7代目社長の諸橋麻貴さんは、その酒質について「先代から伝えられたのは、越乃景虎は脇役で良いということ。料理を引き立て、寄り添う黒子のようなお酒なのです」と語ります。

蔵内にはお酒の販売スペースを用意。約20種類のラインナップから選ぶことができます。
繊細な米の扱いが
味わいを左右する
取材に訪れた当日、蔵は蒸米作業の真っ最中でした。杜氏の浅井さんは、この工程こそが酒造りの味を決める最も重要なポイントだと言います。

使用する酒米は「五百万石」。地元・栃尾産を含む新潟県産米を100%使用しています。
酒造りのマニュアルは、あってないようなもの。浅井さんが杜氏になってから今年で4年目になりますが「毎年、初造りのような気持ちで臨んでいます」と、その仕事の難しさを語ります。
「越乃景虎の特徴は、すっきりした端麗辛口です。水分を吸わせすぎると旨みがのりすぎてしまうので、適量の水分調節をすることでめざす味に近づけます。毎年試行錯誤するのは大変ですが、その分やりがいを感じますね」(浅井さん)

「蒸米堀り」と呼ばれる作業。その名の通り、スコップを使って大量の蒸米を放冷機へ移動させます。体力勝負の力仕事ですが、蔵人は軽々とこなしていました。

機械作業では、気の緩みは危険につながります。蔵の柱には「機械を甘くみるな!巻き込まれ注意」と記した手書きのメモが!

建物2階にある麹部屋へホースで蒸米を送ります。2階からの「温度を下げてください!」との指示を受けて、機械で温度を下げる場面も。鮮やかな連携プレーに思わず目を奪われてしまいました。
よい酒をつくる
杜氏の資質とは?
毎年の酒の出来を決める要素は様々ありますが、杜氏の手腕もそのひとつかもしれません。現在、杜氏として蔵人を先導する浅井さんは、以前は精米会社で働いていましたが、お酒造りに興味をもったことから2005年に諸橋酒造へ入社しました。蔵人となってまもなく、「いずれは杜氏になりたい」と夢を描くようになったそうです。

お酒について語る時、とびきり真剣な表情を見せる浅井さん。酒造りへの熱い情熱が伝わってきます。
杜氏が変わったからといって、その酒質がガラリと変わるわけではありません。しかし「めざす味」は人によって微妙に異なるもので、杜氏の感性が味に影響を与えることは確かでしょう。酒造りは「利き酒で始まって利き酒で終わる」と浅井さんは語ります。いろいろな酒を味わって自分がめざしたい味をイメージし、その年に完成した酒の品質を確かめることで次につなげる。言語化できない酒造り職人の感性は、長年酒造りに真剣に向き合ったからこそ築きあげられた賜物です。

浅野さんが杜氏になって一年目「越後流酒造技術選手権大会」にて新潟県知事賞を受賞しました。
「よいお酒は、蔵人の和がないと造れないんですよ。ギクシャクした雰囲気はお酒の味に影響してしまうんです。杜氏になって4年経ちますが、蔵人たちとの接し方はいまだに試行錯誤ですね。ただ、蔵人たちが自発的に行動し、お互いの考えをシェアし合いながら仕事を進められるのはありがたいなと思っています」(浅井さん)

「留添え」という仕込み後半の作業をする蔵人。ホースを伝って流れてきた蒸米を攪拌しています。一つひとつの工程を大切にし、全員が考えながら行動することで「めざす味」を追求しています。
伝統を守るだけじゃない!
新たな時代の酒づくりに挑戦
170年間に渡る伝統を受け継ぎ、“黒子スタイル”の主役を立てる酒を醸し続けてきた諸橋酒造。しかし、最近は新たなスタイルの日本酒造りにも挑戦しています。

軽い飲み心地のフルーティーな日本酒「越乃景虎 春陽(しゅんよう) 純米酒」。日本酒が苦手な女性にも手に取ってもらいたいと、爽やかなパッケージデザインを採用しました。

「越乃景虎 超辛口大吟醸 無濾過生原酒」は丁寧に贅沢に醸した自慢のお酒。「主役を張れる存在感がありながら、料理も際立たせる絶妙なバランス感に仕上がりました」と浅井さんは胸を張ります。
新商品を世に出すとき、お客さんからの評価は気になるもの。浅井さんは定期的にSNSでお客さんの声をチェックするようにしているそうです。新しい味への新鮮な驚きと感動を示す方もいれば、これまでの越乃景虎のイメージと異なることに戸惑いを感じる方もいるとか……。
「日本酒を飲む方が減っているので、新たな層に届けるためには、これまでと違うコンセプトでお酒を造るのも良いかなと思っています。まずは『越乃景虎』という銘柄を知ってもらい、ぜひ他のシリーズも試してみてほしいですね」(浅井さん)
伝統を守りながら、日本酒の魅力を伝えるために新たな挑戦を始めた諸橋酒造。変わらない部分と変化する部分を見極めることで、古参のファンを大切にしつつ前へ進もうとする強い意志が感じられます。静かに進化を続ける蔵元から目が離せません。
Text&Photo:渡辺まりこ
Information
諸橋酒造
[住所]新潟県長岡市北荷頃408
[電話]0258-52-1151
[URL]http://www.morohashi-shuzo.co.jp/









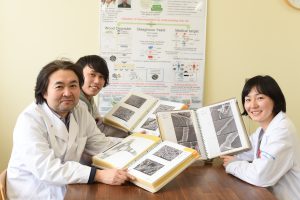










![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)

