バイオ肥料を活用した農業で障害者雇用をオープンに。「夢ガーデン」に見る循環と包摂の未来

SDGs(持続可能な開発目標)という言葉が広く周知されるようになり、企業や自治体もそれぞれの取り組みに着手する中、2021年に内閣府が公募した「地域バイオコミュニティ」に認定された新潟県長岡市でも、企業や大学などと連携し、再生可能な循環型社会を目指そうという機運が高まっています。
長岡市の栃尾エリアにある「夢ガーデン」は、下水汚泥を微生物の力によって発酵分解した肥料やそれを使って育てた山菜・野菜や草花を栽培・販売するほか、地元の食品メーカーと共に開発した加工品などの販売も行う会社。豊かな自然に抱かれた職場環境で、それぞれが得意分野を活かし、のびのびと仕事に励んでいます。大雪が降り続く真冬のある日、夢ガーデンを取材しました。

降りしきる雪が止み、晴れ間が覗いた瞬間。左の茶色い建物が下水汚泥から発酵肥料を作る「緑水コンポストセンター」、右手前が事務所、その奥が肥料を袋詰めする倉庫です。
環境活動に取り組む会社のCSRで
障害者雇用のための「特例子会社」設立
いまから10年を遡る2012年1月、「株式会社夢ガーデン」は緑水工業株式会社のCSR(企業の社会的責任)施策の一環として誕生しました。
長岡市で1959年に創業した緑水工業は上下水道処理施設の運転管理などを担う企業で、県内に5つの営業所と28の事業所を持ち、従業員数は400人超。子どもたちに環境を意識した生活習慣を身につけてもらおうと、上下水道の仕組みを教える出前授業を行ったり、有識者を招いて「水環境フォーラム」を開催したり、環境問題に関わる活動にも熱心に取り組んでいます。
下水処理の過程で発生する汚泥はこれまで焼却、埋め立てで処分、またセメントの材料として活用するなどしてきましたが、環境への影響や埋立地の確保など、課題を抱えていました。処分にかかる多大なエネルギーを削減し、天然由来の廃棄物資源として再利用できないだろうか……。水インフラを起点に循環型社会を志向する緑水工業は検討を重ね、2003年に汚泥をリサイクルして肥料を作るバイオマス事業をスタート。試行錯誤を経て翌2004年に再生素材100%の肥料「かんとりースーパー緑水」が完成しました。新潟県内で発生する汚泥の約1割に当たる年間8000トンから9000トンの下水汚泥を受け入れ、約1400トンの肥料を製造しています。

生活排水を肥料として有効活用するイメージ図(緑水工業のウェブサイトより)
「“汚泥から作られた肥料”と聞けば、なんとなくマイナスのイメージを持つ人もいますよね。しかし汚泥には、植物の成長に欠かせない窒素・リン酸・カリウムという有効成分が含まれていて、野菜や草花がよく育つから、うちの肥料はリピーターが多いんですよ。品質管理を徹底しているので安心して使ってほしいです」(野口さん)
リン鉱石の採掘がない日本は輸入に頼っていて、世界的にも資源が枯渇している状態。地球環境のためにも、農業を維持するためにも、汚泥のリサイクルが力を発揮します。

左が株式会社夢ガーデン代表取締役社長の野口邦夫さん。お隣の髙山嘉幸さんは栃尾出身で、広報宣伝や営業など、社長の右腕として活躍しています。社長いわく「地元に顔が利くからね、ここに必要な人」とのこと。
「最近新しい従業員が入って、障害のある人が8人になりました。聴覚障害、身体障害、知的障害、精神障害など、その内容は人それぞれですから、ひとくくりにはできません。仕事としては、肥料の袋詰めに配達、山菜・野菜の栽培、そして木工も。コミュニケーションが難しいこともあるけど、得意なこと、できることをやってもらえれば。重機を使っている場所もあるから、とにかく事故やケガがないようにと、それだけは気をつけています。それぞれの特性を把握することが大事です」(野口さん)
畑に家庭菜園、公園にも!
安全性、破格の安さも魅力の万能肥料
さっそく、肥料を製造するコンポストセンターから倉庫、山菜が栽培されているビニールハウス、木工品を作っている工房まで、野口さんに案内していただきました。

「これが緑水コンポストセンター。この中で肥料を作っています」と野口さん。

モワッと温かく、ほのかにアンモニア臭がするコンポストセンターの内部。運び込まれた汚泥に自然由来の微生物を入れて何度も攪拌し、高温で発酵熟成させます。

「この袋詰め作業を障害のある人が担当してます」。完成した肥料はサラサラで匂いもありません。袋を持参し、スコップですくって自分で詰めると、なんと1袋50円!セルフなのでお金も自分で箱の中へ。

袋詰めされ、出荷を待つ「かんとりースーパー緑水」(15kg入り袋250円)。業務用の350kg入り袋は1500円、650kg入り袋は2000円。安い!

「長野県の畑とかゴルフ場とか、肥料を積んで1日50トンくらい撒きに行くこともあります。売るためにはそれくらいやらんとね(笑)。痩せた土地でも、これを撒くと土がよくなって、いい野菜になるんです」
耕作放棄地を農業で再生し
障害のある人たちの雇用を生む
続いて、早春の山菜「行者にんにく」と「うるい」が収穫シーズンを迎えているビニールハウスへ。雪の多い冬場はハウス栽培の山菜や雪の下で越冬させる「雪下にんじん」などを収穫しますが、春から秋にかけては農業者の高齢化や後継者不足に伴って増えている耕作放棄地や荒れた山林を活用し、「かんとりースーパー緑水」を使って野菜を育てています。キノコや花も入れると、栽培しているのは年間50品目にもなるのだとか。
ここで農業に従事している太刀川拓也さんは長岡出身の28歳。夢ガーデン設立時に就職して10年になるそうです。
「障害者就職面接会で、社長さんにスカウトされたんです。それまで農業はやったことがなくて、ここで初めて農業のいろはを学びました。決して1人でやれる仕事ではないし、力を合わせればいいという仕事でもないです」(太刀川さん)

「行者にんにくも、うるいも、この辺では珍しいですよね。ここに来るまで食べたことなかったです。育て方の工夫で野菜は美味しくなるのかも」と微笑む太刀川さん。

髙山さんと一緒に、うるいの温床にカバーをかける太刀川さん。外は大雪ですが、ハウスに足を踏み入れると瑞々しいグリーンが目に鮮やかで、春の薫りが漂っていました。
ハウスを後にして、最後に訪ねたのが事務所2階にある工房。雪国では昔から農閑期に手仕事が行われてきましたが、ここではプランターや表札など木工品の制作が行われ、ギュイーンという電動ドリルの音が響いています。

工房では聴覚障害のある武藤哲夫さんが大活躍。長岡聾学校で木工を習っていたそうで、丁寧に仕上げられた木工品の出来栄えに驚かされます。

愛らしいデザインのプランター、オーダーに応えて制作している表札。
地域の人々と交流し、企業とは商品開発
市内の経済循環にこだわる未来づくり
取材時は見渡す限り厚い雪に覆われていましたが、約2.7haの農地には花畑もあり、ユリやハスなどを栽培しています。秋にはサツマイモが実り、市内の幼稚園児たちが芋掘りにやって来るそうです。


「木工のプランターを買ってもらった縁で、芋掘り体験を実施しました。子どもがいる風景、はしゃぐ声はいいよね」と野口さん。

冬から春にかけて、うるい、行者にんにく、ウドやワラビなどの山菜も出荷しています。

夢ガーデンと地元メーカーとのコラボレーションで完成した人気商品の数々。ラベルは障害者の就労支援施設「Oneながおか」が手がけ、「おかずみそ」と「もつ煮込み」は長岡市のふるさと納税返礼品にもなっています。

夢ガーデンで収穫した落花生「おおまさり」を使った「おおまさりあられ」。生産量が少ないため販売店には出していないレアものだとか。
「芋掘りに来てもらったり、重機を使って近所の集落の落ち葉を片付けたり、ボランティアでいろいろやっていますが、金にならんことばっかりでね(笑)。夢ガーデンの売上だけではなかなか難しくて、親会社である緑水工業から委託費を受け取っているから成り立っていて、どうにか従業員の給料が支払えます。本当は夢ガーデンの売上を独立させて、みんなの給料をもっとアップしてあげたいと思うし、そのためにも山菜・野菜や加工品をもっと積極的にPRしていきたいですね」
自由なアイデアと軽やかなフットワークで次々に楽しい企画が生まれています。夢ガーデンの入り口に、まもなく直売所がオープン予定だとか。四季折々の花や旬の採れたて農産物に出会える“夢の庭”は、シーズンごとに訪ねたい場所になりそうです。

豪雪地域・栃尾らしい真冬の1日。取材中に雪下ろし風景も見られました。Facebookによれば「除雪も楽しい!」そうです。
Text: 松丸亜希子 / Photo: 池戸煕邦
(商品写真等は夢ガーデンのFacebookからお借りしました)
●インフォメーション
夢ガーデン
[住所]新潟県長岡市北荷頃1517-2 緑水工業コンポストセンター内
[電話番号]0258-51-1150
[Facebook]https://www.facebook.com/株式会社-夢ガーデン-106846444200472/
[URL]http://www.ryokusui-k.co.jp(緑水工業)







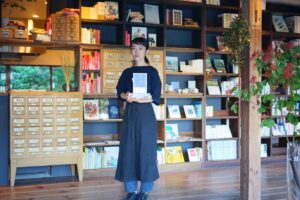












![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)

