【公開取材レポートvol.1】 長岡を出た若者たちが語る「離れても地元と関わり続ける生き方」の可能性

この記事は「な!ナガオカ」の新たな試みであるオンライン公開取材の内容をもとに作成しています。本企画は取材と同時に、長岡市に拠点やゆかりを持ちながら普段なかなか出会うことのない人たちや視聴者をオンラインでつなぎ、それぞれの「点」が「線」や「面」になるような、長岡ならではのユニークな広がりとなっていくきっかけを作るため、「な!」編集部をホストに不定期で開催していきます。

「離れても地元と関わり続ける」
そんな生き方は可能か?
高校を卒業したら大学進学のために上京して、そのまま東京で就職する、という話は、長岡のみならず、東京までのアクセスもいい新潟県ではよくある話。そして、「いつかは地元に」と心のどこかで故郷をいつも気にしながらも、東京での暮らしが長くなればなるほど、完全に拠点を地元に戻すというのもなかなか思い切りが必要になってくる。
一旦地元を離れても、再び繋がりを持つ方法はあるのだろうか。そして、それは外からでも可能なのだろうか。今回は、そんな地元との関わり方をテーマに、長岡以外の地を拠点としながらも、遠隔で実家の家業に携わっているお二人にお話をうかがった。
当たり前のように長岡を離れた
“東京に出た息子”たち
地元を離れると、本人の中にも、そして送り出した家族の中にも生まれるのが、戻るのか否か、という問題。出る時はいつでも戻れるような気持ちでいるのに、いつの間にか実家という一点のみ繋がって、地元との距離は精神的にもいつの間にか離れてしまう。そして、故郷として大切には思いながらも、“戻る”という決断のハードルは、いつの間にか高くなっているのだ。
でも、ちょっと待てよ。地元との関わり方は、「戻るor 戻らない」の2択しかないのだろうか。
今回は、進学を機に長岡を出て、今も拠点は外に持っているお二方にお話をお聞きしながら、その疑問と向き合ってみたい。まずは、お二人を紹介しよう。
現在、岩手県遠野市でローカルプロデューサーとして活動する富川岳さん。大学進学をきっかけに長岡を出て、卒業後は東京の広告代理店で様々な広告企画を担当してきた。30歳手前で遠野市でプロジェクトの立ち上げに携わることになり、それをきっかけに現地に移住。現在は、「地域文化×デザイン」を軸に、岩手県の文化や産品をデザインの力で広く届ける活動を行なっている。

お相手は、東京でウェブデザイナーとして活動する早川雄大さん。大学進学を機に上京し、卒業後はデザインの道へ。グラフィックに留まらず、エディトリアルデザイン、WEBサイトのディレクションなど、ジャンルレスに幅広いプロジェクトに関わっている。

長岡で生まれ(奇遇にも、小中高校の先輩後輩にあたることが発覚!)、当然のように「外に出るものだ」と決めて市外に進学、東京で社会人としての一歩を踏み出したお二人だが、もう一つ共通点として注目したいのが、長岡の実家がそれぞれ地元で家業を営んでおり、住まい自体は長岡になくとも、継続的に遠隔でそれぞれの家業に携わっているということだ。実家を出てしばらく経ってから、地元に戻らずとも家業に関わろうと思ったのには、どんなきっかけがあったのだろう。そして、その関わりはどのようなものなのだろうか。
デジタルとアナログの合わせ技で
実家のビジネスを支える
まずは富川さんのケースから。1987年生まれの富川さんは、ご実家である長岡の老舗割烹「富川屋」で、2016年からご両親が作る「鮭の味噌漬け」のオンライン販売を行っている。

「東京で働く中で『地方で仕事をする』ということに興味を持ち始めた頃、長岡を含めて移住先をいろいろ考えるなかで、実家のことを全然できていないな……って、不甲斐なさみたいなものを感じていたんです。そんな時、ふと、両親が作って送ってくれた鮭の味噌漬けをお土産や贈り物としていろんな方に食べていただくたびに『美味しい!』と言っていただけたことを思い出して。
常々、見せ方や届け方を工夫することによって地元のいいものが残っていくのであれば、それは自分がやるべきことだと思っていたところだったので、その一つとして可能性を感じたのが、この味噌漬けでした。遠くの方にもオンラインで販売したらもっと多くの方に食べてもらえるんじゃないか、っていうシンプルな発想なんですけど。最初、両親は『顔の見えるお客さん相手に商売してきたんだから、そんなことしなくていいよ』と反対だったんですが、それを押し切って、半ば強引に始めちゃいました(笑)」(富川)
このオンライン販売のおもしろいところは、デジタルなようで、実はやりとりがとてもアナログであるという点だ。買いたい人がアクセスするのは「BASE」というショッピングサイト制作サービスで作った特設ページであり、購入の流れは通常のオンラインショッピングとさほど変わらない。しかし、ユニークなのは裏側の動き。商品の購入があったという通知は、まず遠野にいる富川さんに届く。そして、次に富川さんが、その注文キャプチャ画面を長岡にいるお姉さんにLINEで送信。その内容をお姉さんからご両親へ口頭で伝えて味噌漬けを仕込み、数日後に長岡から購入者に発送される、という流れなのだ。家族間での伝達リレーによって成り立っているという背景を知ると、単にオンラインで物を買うのとは少し違う温かみが伝わってくる。
「味の感想など、いい反響は姉に送って、それを親に見せてもらうということを地道に続けていくうちに、最初は反対していた両親も喜んでくれるようになって、今に至っています。本当は問い合わせメールの対応から親や姉ができたらいいんですけど、スマホの操作もなかなか難しいですからね。今は、自分が仕事しながらでもできるレベルの注文数なので、このスタイルで細々とやっていこうかなと思っています。仕出し割烹としての家業は継げなくても、この鮭の味噌漬けの作り方や味は『富川屋の味』(富川さんが遠野で経営するブランディング会社の屋号も「富川屋」。富川さんの思いが窺える)として引き継ぎたいと思っています」(富川)

お米のことを知って初めて
選ぶ楽しさを伝えたくなった
一方、早川さんのご実家は、長岡でお米の問屋と卸しをしている「早川米穀店」。お二人が同じ小学校出身というだけあって、富川屋にもお米を納めているという地元ならではのつながりがある。
1996年生まれの早川さんは、昨年、実家のお米を新しい顧客層に届けたいと『まっしろ』という新しいブランドを立ち上げた。1パック2キロを基本のパッケージとして、単品購入も可能な他、毎月、あるいは二ヶ月に一回の定期便対応もしている。
「それまでは、こんな形で実家を手伝おうなんて思ってもいませんでした。ですが、昨年の3月、たまたま仕事で新潟を訪れたので実家に立ち寄っていたら、そこで新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が出てしまって。6月上旬までの約3ヶ月、東京に帰れなくなってしまったんです。さらには、東京に帰ってきてすぐに父が脳梗塞で倒れて、再び実家を1ヶ月手伝うことになって。思いがけず久しぶりに実家に長期間いる中で、家の仕事を初めてちゃんと見る時間も取れて、あらためてお米のことを知ることができました。そこで生まれたのが、『お米をシーンで選ぶ』という発想でした。
朝と夜の2種類で展開しているんですけど、朝はお弁当にもしやすいよう冷めてもおいしいお米を、夜はいろいろな料理に合うお米をそれぞれセレクトしています。ひとつの量を一人暮らしの人が1ヶ月で食べきる2キロにしたのは、お米も生鮮食品だから。通常スーパーなどでは5キロの袋で売っていたりしますが、それだと一人暮らしではなかなか消費しきれないので、新鮮なうちに食べきれる量にしました。パッケージには本の装画などで活躍する安達茉莉子さんのかわいらしいイラストを採用し、haru.による文章を添えたりもしています。単なる食品というよりも少し雑貨などに近いイメージにすることで、若い世代にも手に取ってもらえたらいいなと思って」(早川)

一般的には、「おいしいお米」の基準とされているものは産地や品種、あるいは等級や水分含有量といった「固い言葉」や単なるデータであることが多い。だが、それでは若い人にはなかなか届かない。もっと「やわらかい言葉」とイメージを提案することで、特に「コメ離れ」が進む若い人たちに対して、お米を選ぶ楽しさを伝えたかった、と早川さん。
「上京してから自分の周りを見ていても、お米がちゃんと選ばれていないと感じることがあって、そのことへの問題意識みたいなものはずっと持っていたんです。ただ、そういう自分も、米屋の息子なのに米のこともわからないし、精米もできなければフォークリフトにも乗れないという有様。でも昨年、実家にいる間に家業を手伝ったことによって、お米って実は個性豊かで、選び方によっても楽しめるものだっていうことを、私自身も気づいたんです。それを、特に自分と同世代の人たちにも知ってほしいと思ったことが、このブランドの誕生に繋がりました。これからも、新潟の米、長岡の米を広める活動をしていきたいと思っています」(早川)
内と外が程よく混じり合う
フラットな場所が必要
富川さんと早川さんは、どちらも家業があることによって、現在、地元との繋がりを再び持つことができている。しかし、世の中には実家が家業を持たないという人が大半なはずで、そういう人は一度都会に出てしまうと接点を持ちづらいというのも事実だろう。
そもそも、若者が地方都市を出る理由としては、「この場所では自分の将来像が見えない」と思ってしまうことが大きい。観測範囲にいる人々の職業や生き方だけがサンプルになってしまうと、そうではないものを志向する人は「ここを出なければならない」という気持ちにもなるだろう。それ自体は、もちろん「何も悪いことではない」と富川さんは言う。
だが、そうした人々が外に出たことで得ることができた知識があり、離れたから見えてくる地元の良さもあるはずなのに、それを生かすきっかけが掴めないというのは、地方都市にとっても、都会で暮らす出身者にとっても、もったいないことのように思えてしまう。
では、外に出た人が再び故郷と接点を持つには、なにが必要なのか。自分自身が移住者として遠野市で暮らす富川さんならではの視点に、その大きなヒントがあった。
「自分は確かに家業を手伝ってはいますが、なにせ高校卒業とともに出ているので、長岡のことを実はそれほど知らないんですよね。地元に残っている同級生と会うと懐かしいし楽しいけど、それぞれに積み重ねてきた時間や感覚があるから、何を話していいかわからないという感覚がある。そういう点では、IターンとかUターンで一度出た経験がある人の方が話がしやすい、ということもあると思います。
遠野の僕の事務所は通り沿いの1階にあって、外から丸見えだし、誰でも入れるオープンな感じがあるからか、東京に出ていた遠野出身者が帰省した際に立ち寄ってくれたりするんです。それで、僕が地元出身の方に「今の遠野はこうなってますよ」といった情報をお教えするということもあって。仲のいいお店でも何でも、実家以外にそういう立ち寄りやすいフラットな場所があると、外に出てからでも地元との繋がりを意識しやすいのかもしれないなと思います」(富川)

人がいて、情報があって、その接点を作ることができる場所。そういう場所があれば多様な生き方をしている人々のサンプルと出会うことができ、地元に満足できない若者たちも「地方にいても、こういう面白いことがやれるかもしれない」という新しい視点で地元を見ることができるかもしれない。
早川さんも、「点と点を繋いでいくようなコミュニティが必要」と続く。
「富川さんの事務所って、まさに人と人のハブになっているんだと思います。単に箱があればいいということではないと思いますけど、中にいる人、外に出た人の両方のことを知れるような場所や、オフラインで繋がれるコミュニティがあるといいですよね。長岡造形大学や長岡技術科学大学などの学生を巻き込んで、みんなで場所を作るのもいいかもしれません。長岡には、すでにコンテンツの力としては十分なものがあります。花火もあって、海も山もあって、お米やお酒もある。バスケもプロチームがあるし、近頃は高校サッカーも強い。じゃあ、何が足りないか、何が必要かって、やっぱり人と繋がれる場所や繋がれるきっかけだと思います」(早川)
人間の幸福には「家」と「勤務先」の往復だけでなく、喫茶店や公園など、そのどちらにも属さない場所やコミュニティのある「サードプレイス」が必要だと言われている。同じように、故郷を出た人がなかなか戻ってこないという問題には、実家やその周辺といった場所以外の居場所、いわば都会と地元の間の「サードプレイス」づくりが有効なのかもしれない。そこに必要なのは、地元感100%の場所ではなくて、出身者も移住者も、学生も社会人も、拠点を他の場所に持つ人も、いろいろな人が立ち寄って混ざり合っていくような多様さ。富川さんが話してくれた“フラットな場所”こそ、外と内の重要なハブとなり、長岡と人との繋がりを一層広げる鍵となりそうだ。
「好き」を軸に関わる人こそ
地元の財産になる
遠野市で行政とのプロジェクトにも携わっているという富川さんは、その経験からこんなことを話してくれた。
「市役所など行政でお仕事をされてる方って、生まれも育ちも地元で、外に出ていない方が多いような気がします。移住とか観光に関する仕事も、移住者や観光客の目線がないままに施策を考えなくてはならない。それでは職員の方も大変でしょうし、いいアイディアも生まれにくいんですよね。そういうところで重要なのが、外に出た経験じゃないかと思います。その経験があることで客観的に土地のことを見ることができますし、他の地域と比べることもできますしね。だから、外から人を呼ぶ、外に向けて発信する、みたいなことを考えるには、外に出たことのある人の視点を織り交ぜて手を組んでいくのがいいのかなと。主観と客観。そのどちらも必要で、どちらが欠けてもダメなんです。そういうことができるかどうかで、各地の行政が『イケてる行政』とそうでない行政に二分化しつつあるというのも感じますね」(富川)
外に出た経験や外にいることは、むしろメリットかもしれない。早川さんは、富川さんの話を聞いて、自分たちこそ力になれるかもしれないと気づいたようだ。
「長岡の外に出ていろんなものを見たり経験したりして、今こうして地元のことにも片足を突っ込んでいる。そんな僕たちみたいな人が重要っていうことですよね。必ずしも長岡に住んでいなくても、外に出た経験のある人が集まってアイディアを考えられたら、いいものができそうな気がします。地元の人も外の人も、いろいろなジャンルで活躍している人を集めて、多種多様な視点から長岡について考えて議論する。そういうチームみたいなものを作れたらおもしろそうじゃないですか」(早川)

「住む」ことだけが街に関わることではない。長岡にいないと関われないのではなくて、いなくてもアイディア次第で関われることがある。現在、居住はしていなくても地域に出入りして関わりを持つ「関係人口」という言葉がまちづくりの分野で注目されているように、出身者だけでなく、花火が好き、お酒が好き、ごはんが好きなど、“好き”を軸に集まってくる人たちの力も必要なのだ。大切なのは、関わりたいと思っている人たちを、どう繋げ、どう広げ、どう手を組んでいくか。そこには、行政や長岡に住んでいる人たちの理解や興味、外の人と一緒になにかやってみたい、というオープンマインドも必要になってくるのかもしれない。
話題は行政による政策デザインや意思決定フローの重要性といったことにも広がり、お二人ならではなアイデアも次々に飛び出すエキサイティングなひとときとなった(この記事だけでは全ての内容はとても紹介しきれないので、アーカイブ動画をご覧いただきたい)。最後の最後は「長岡のこと、めちゃめちゃ携わりたいです!」と早川さん。「早川さんにやってほしいなぁ!もちろん僕も手伝いますけど(笑)」と富川さん。お二人のお話を聞いていると、外にいても、いや外にいるからこその長岡愛が、長岡という土地を魅力的に発信したり、眠っていた良さを鮮やかに目覚めさせたりするのかもしれない、と希望が見えてきた。「ぜひ、長岡で会いましょう!」そう言い合って、この公開取材は幕を閉じた。このお二人が、今後長岡とどう関わっていくのか、次の展開からも目が離せない。
※本イベントの全内容はこちらのリンクでアーカイブ視聴できます。
https://youtu.be/o4jNKvmt6wE
text : 内海織加







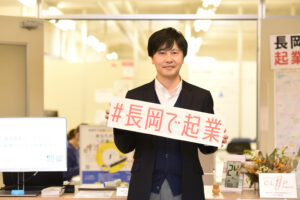












![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)

