市民の“知りたい気持ち”に応えたい! 8部門もの「ハカセ」に会える長岡市立科学博物館【後編】

地学・植物・動物・昆虫と考古・歴史・民俗・文化財、これら8つの研究室を持ち、各分野のエキスパートが活躍する長岡市立科学博物館(以下、長岡科博)。その取り組みを取材し、前後編に分けてお届けします。
前編では、長岡科博を訪ねて総括副主幹の田中洋史さんに歴史や概要について伺い、開催中の企画展『長岡カブト・クワガタ学』を担当する昆虫研究室の学芸員、星野光之介さんにインタビューしました。後編は、6月22日に開催された動物研究室の野外イベント「生きものガイド:会えるかな? 森のカエルたち」のレポートです。
生きもの好きな未来の研究者たちと
森に棲む両生類を探しに自然観察林へ
長岡科博では、展示室を使ったさまざまな展示はもちろん、知的好奇心に応えるイベントを8つの研究室が企画運営し、市民の知りたい・学びたい気持ちに応えています。そのうちの一つである動物研究室では、子ども向け生きもの講座、大人向け講座、県内外から外部研究者を招いた講演会、探鳥会など、年齢問わず参加できるバラエティに富んだイベントを展開中です。
今回取材したのは、小学3年生以上の子どもと保護者を対象に開催された「生きものガイド」です。テーマは“森のカエル”。モリアオガエルなど県内で減少している両生類をみんなで探して観察しようという企画です。
JR長岡駅東口から南東へ車で15分ほどの場所にある、東山ファミリーランド自然観察林に向かいました。ガイドしてくれるのは長岡科博の学芸員、動物研究室の鳥居憲親(のりちか)さんと植物研究室の櫻井幸枝さんです。

駐車場から緑あふれる森の中へ。先導する鳥居さんに続き、足元の草をかき分け進みます。

この日は梅雨の晴れ間で、「お天気でよかった〜」と思っていたら、「カエルを見つけるなら、薄曇りで湿気があるほうがいいんですよ」と鳥居さん。カエルの野外観察会は時期が早いと産卵が始まっておらず、遅いと気温が高くなってカエルがいないなど、日程を決めるのが難しいのだとか。さて、今日はどんな生きものに出会えるでしょうか。

長靴を履き、たも網を準備する子どもたち。みんな生きものが大好きなようで、会場に到着して早々、「あ! モリアオガエルの卵塊(らんかい)だ!」という声が聞こえてきました。
「わぁ、詳しいんだね。モリアオガエルは新潟県のこの辺りではまだ比較的よく見るんですけど、全国的にはかなり数が減っているカエルです」と鳥居さん。

「モリアオガエルは背中が緑色、おなかが白いカエルで、ふだんは木の上にいますが、この時期だけ山間の水辺にやってきて、白い泡(泡巣)の中に300個ぐらいの卵を産みます。泡巣があそこにぶら下がってますが、そろそろ泡の中で卵がかえって、オタマジャクシが池の中に落ちてくるころです。けっこう上のほうまで産みに来ていて、測ってみたところ、いちばん高いところは20メートルほどありました。生まれたばかりのオタマジャクシはいきなり20メートルも下の池にダイブしないといけない。すごいスパルタですね(笑)。オタマジャクシは夏の間に成長してカエルになり、秋になるとまた森の中に姿を消してしまうので、モリアオガエルはこの時期じゃないとなかなか見つけられません。今日は気温が高いのでどうかな、見つかるかな。みなさん、がんばって探してみてくださいね」(鳥居さん)

「僕は県外出身で、こっちに来てモリアオガエルを見てびっくりしました。僕が知っているモリアオガエルの背中には鉄が錆びたような茶色のマダラ模様があり、目も赤いです。全国的にはそちらが主流なのですが、新潟県周辺のモリアオガエルは背中にマダラ模様がなくぜんぶ緑色で、目の赤みも少なくて、ちょっと黄色に近い。シュレーゲルアオガエルによく似ています」(鳥居さん)

「ここにはカエル以外の両生類もいます。なにか生きものを見つけたら、このバケツに入れてみんなで観察しましょう。カエルを捕まえた人はバケツに入れる前にスタッフに言ってくださいね。ふたをしないと飛び出しちゃうので、『あれ? 捕まえたはずのカエルがいないよ』ということが起こります。では、カエル探し、お願いします!」
鳥居さんの合図で、思い思いの場所へ走り出す子どもたち。網を使って池や沢を探り始めました。
オタマ、イモリ、サンショウウオ
そしてカエルは……?
池の中でなにやらピチピチと動いているものが見えました。子どもたちが「あ、なんかいる!」と網ですくってみると、オタマジャクシが入っていたり、枯れ葉だけだったり。捕獲した生きものはどんどんバケツに入れていきます。

池をのぞき込み、「わぁ、オタマジャクシばっかり! ゲンゴロウや魚はいないのかな」と言う子ども。いまは卵がかえる時期なのでオタマだらけですが、ここにはヤゴなどオタマを食べる生きものもいます。「ヤゴはバケツの中に入れないでね。オタマが食べられてしまうから。ゲンゴロウはどうかなぁ。ゲンゴロウもすごく数が減ってるんですよ」と鳥居さん。
さて、お目当てのカエルはどこにいるのでしょう。
「トノサマガエルは田んぼなど水辺の近くにいますが、モリアオガエルは産卵の時期だけ水辺にいて、それが済むと森の中に帰っていきます。どうやって卵を産む場所を決めているかというと……葉っぱの裏側に水の影が反射してキラキラしてるのが見えますか? 水のゆらめきが映っていると、その下に水があるなとわかり、それを目印にしてモリアオガエルのメスは木を登ります。一方、食べたものを調べてみると、木の上のほうに飛んでいる小さなハエなどをいっぱい食べているようです。ただし、葉っぱの重なり合う日陰になっている場所に隠れているようで、ドローンを飛ばしてみてもなかなか見つからないそうです」(鳥居さん)

子どもたちは水の中に集中していますが、上空からは鳥たちの賑やかな声も聞こえます。
「ここは鳥もいっぱいいて、地元の野鳥の会さんと毎月開催している探鳥会でも来るのですが、いま『ホイホイホイ』って鳴いているのがサンコウチョウ。東南アジアからやってくる尾羽の長い鳥です。さっきカワセミもいましたよ。あ、あそこに! 自転車の急ブレーキのような『キーッ』という音、これがカワセミの鳴き声です。あれはオスですね。上下のくちばしがありますが、オスは両方とも黒。メスは下のくちばしがオレンジ色で、『口紅をつけていたらメス』と覚えてもらえるといいと思います」と鳥居さん。さすが鳥類の専門家です。
「なんかいたよー。あ、イモリだ!」という子どもの声がして、駆けつけてみるとゴソゴソ蠢く黒いものが網の中に。

「ヤモリとよく間違われるけど、爬虫類のヤモリは水辺にはいません。イモリは両生類で、水の中で暮らしています。イモリと見た目が似ているサンショウウオは、柔らかい地面の中や倒木の下などに潜って冬眠するんです。種類によって棲んでいる場所が違います」(鳥居さん)
バケツの中には、子どもたちが捕ったオタマジャクシやイモリがたくさん。1時間ほどが経過しましたが、モリアオガエルはなかなか見つかりません。そこで、水辺の近くの茂みを探してみると、子どもたちの「あ、あそこにカエルがいる!」「どれどれ?」「枝を登ってるね」という声が。何度か逃げられた末、ようやく何匹か捕獲に成功したようです。お目当てのモリアオガエルでしょうか? いよいよ観察タイムの始まりです。
はい、みんな集合〜!
森の生きものを観察しよう
鳥居さんが「いったん集まって、生きものを観察してみましょう」と呼びかけます。
さてさて、どんなものが捕れたでしょう。鳥居さんと櫻井さんが生きものをバケツから観察用のビンに移し、ふたのラベルにそれぞれの名称を書き込んでくれました。


「おかげでカエルもなんとか捕獲できました。これはモリアオガエルのオスかな。メスのほうが大きいのですが、このカエルはだいぶ小さいのでオスじゃないかな。ビンを回して、ぜひいろいろな角度から見てみてください」と鳥居さん。
「わー、すごい、すごい!」「きれいだね、ツヤツヤしてる」「かわいい〜!」と、歓声が上がりました。

「よく間違われるのですが、みなさんのおうちの近くにいるのはニホンアマガエル(正式名称:ヒガシニホンアマガエル)です。同じ緑色だけど、目の横に茶色っぽい線が1本入っています。博物館に『近所でモリアオガエルを見つけました』と言って持ってきてくださるんですけど、ほとんどはこのニホンアマガエルです。ツチガエルも回しますね。ぜひ見比べてみてください」(鳥居さん)


「見比べてみて、気づいたことはありますか?」という鳥居さんの質問に、「ツチガエルはボコボコしてる」「シマシマがある」「ツチガエルには吸盤がない」と子どもたち。
「はい、正解です。足のシマシマ模様と背中のボコボコはツチガエルの特徴で、別名イボガエルと呼ばれることもありますね。そして吸盤の有無。ニホンアマガエルとモリアオガエルはビンの内側を登ろうとしますが、ツチガエルは吸盤がないので登れません」
「ツチガエルはなにを食べるかな?」という質問に「アリ!」と即答する子どもたち。「そう、木に登れないので、地面にいるアリや小さいコオロギなどを食べます。モリアオガエルは木登りができるから、木の上のほうを飛んでいるハエや蚊などを食べられるし、高い場所にも卵が産めるんですね」
「では、もう1つ質問。カエルの指は何本か知ってる人?」という難問に「はい! 前が4本、後ろが5本」とまたもや即答。子どもたちの、大人顔負けの知識量にびっくりです。
「そうです、正解。すごいですね。指の本数はすべてのカエルに共通なので、よく見てみてください。みんなががんばって捕ってくれたイモリも回しますね」と鳥居さん。

「オタマジャクシは2種類見つかりました。モリアオガエルとクロサンショウウオです。オタマジャクシというのはカエルだけでなく両生類の幼体の総称で、サンショウウオには顔の後ろにヒラヒラした襟巻きみたいなエラがあり、そのエラで呼吸をしています。クロサンショウウオは水中に落ちた枝などにアケビ状の卵塊を産みます。カエルのオタマは最初に後ろ足が生えますが、サンショウウオは前足から生える。そんな違いもあります。セットで回すので見比べてみてください」(鳥居さん)

「クロサンショウウオはエラがなくなって肺呼吸ができるようになると水から上がり、倒木や土に潜って冬眠して春にまた水辺に戻って産卵するんです。オタマが出た後の泡巣も回すので、触りたい人は触ってみてください」(鳥居さん)

「最後に、みなさんにお願いがあります。今日はたくさんの両生類を観察してもらいましたが、両生類は全国的に急速に数が減っています。水辺も森も両方ないと暮らせないため、そのバランスが崩れると森の両生類はいなくなってしまうんです。今日観察した中だと、クロサンショウウオとアカハライモリは新潟県の絶滅危惧種になっていますし、モリアオガエルは長岡市の希少生物にも指定されています。みなさんが大人になるころには、もうここにいないかもしれない。そんな両生類をなんとかして守っていきたいね、ということで今日のイベントを開きました。この自然観察林は通常は生きものの採取は禁止ですが、両生類の現状を伝えるための活動ということで、特別に一時捕獲を許可してもらいました。生物の持ち帰りはできないので、観察や写真を撮り終わったら元いた池や沢に返してくださいね」(鳥居さん)

参加者との「気持ちの近さ」で
学びを応援するのが長岡科博の役割
終了後、参加者のみなさんに感想を伺いました。
「長岡科博のイベントは、雪の下からドングリを探すという真冬のイベントに参加して、今日が2回目。うちの子は生きものが大好きなので楽しんだようです」
「いろんな自然の生きものをじっくり観察できたし、棲んでいる場所を知ることができて、すごく勉強になりました」
新潟市から参加した親子も。お母さんいわく「この子が2歳のころから生きもの、特にカエルが好きで、以前アズマヒキガエルを飼ったこともあるし、今年はうちでカエルの産卵が見られて喜んでいました。今回は“新潟 モリアオガエル”で検索したら、このイベントがヒットしたので来てみました。自分たちでやっても限界があるから、こういうイベントは素敵だなと思います」とのこと。
お話を聞いている間に、隣にいたお子さんが網をサッとひと振りして、なにかをキャッチ!

鳥類の研究者である鳥居さんは、ご自身の専門分野を超えたイベントの運営について、こう考えているそうです。
「教科書に載っているものは学校で教えてくれますが、載っていないものはなかなか教えてもらう機会がありません。例えば、カエルについて知りたいと思っても学ぶ場がないというのは、本当にカエルを知りたいと思っている子どもたちにはとても辛いこと。『知りたいならいつでも博物館においで。答えを一緒に見つけよう』、そう言ってあげられる場所に長岡科博がなれたらと思っています。動物研究室は僕1人しかいないので、鳥類に限らず、教科書の外にいるいろいろな動物たちの世界をご案内していけたらいいなと考えています」
新潟県内の「愛鳥モデル校(鳥を愛し、鳥に関する活動を積極的に行っている学校)」でも講師を務めている鳥居さん。「カエルと同じく、小学校の教科書では鳥類も扱いません。でも、知りたい子がいたらその学びを応援するのが私たちの役目だと思っています」
長岡科博には、子どもだけでなく、大人向けの生きものの企画もたくさんあります。「『生きものを知るたび、“もっと知りたい”が見つかる』をキーワードに、植物研究室の櫻井と一緒に『ネイチャーセミナー』をやっています。大人向けのイベントを増やしてほしいというリクエストを受け、今年度は大人向けの講座を拡充しました」

動物研究室との合同で、ネイチャーセミナーの企画運営をする櫻井さんはこう語ります。
「博物館のイベントには、参加者の方と一緒に生きものを見て、発見やその感動を共有できる楽しみがあります。同じ生きものを見てもスタッフと違う発見をする方もいて、驚かされることがあるんです。植物も動物も、じっくり観察するところがスタート。生き方やおもしろさが伝わるような会にしていけたらいいなと思っています」
おふたりは「こんなことをやってほしい」というリクエストを参加者から受けると、それにできるだけ応えようと相談して内容を決めているのだとか。
「1つの視点だけでなく、その生きものを取り巻くいろいろなことにも興味をもってもらえたらと思っています。そのほうがおもしろいし、こんなのもあるよ、もっとこんな世界もあるよと、たくさんの発見がある場を提供していきたいです」と鳥居さん。
「この場所を使って、一緒になにかやりませんか」と、市内に店舗を構えるジェラート店の有志の畑づくりチーム「ジェラート雪鹿Field Lovers」からオファーが入り、共催イベントがスタートしたり、未来里山技術機構と一緒に里山の未来について考えるトークセッションをこの秋に開催したり、ほかの組織との連携でさらなる広がりも生まれています。
74年前の夏、野鳥の愛好家たちが願って開館に至った長岡市立科学博物館。市民との距離の近さはいまも変わらず、市民に愛される博物館としてこれからも活動は続きます。

Text: 松丸亜希子 / Photo: 池戸煕邦
長岡市立科学博物館

住 所
新潟県長岡市幸町2-1-1、さいわいプラザ1階
電話番号
0258-32-0546
営業時間
9:00〜17:00(入館は16:30まで)
定休日
第1・第3月曜日(祝日等の場合は翌日)、12/28〜翌年1/4 ※8月は無休
イベント
9月15日(月・祝)まで企画展『長岡カブト・クワガタ学』を開催中。10月25日(土)〜12月27日(土)は企画展『なつかしのおかしとおさべ菓子店-おかしにつまった栃尾の思い出-』、11月3日(月・祝)14:00〜15:30に関連イベント『職人の技が光る!巻鯛作りを見学しよう!』。
さいわいプラザ3階の長岡藩主牧野家史料館では、9月21日(日)まで特別展示『牧野家に嫁いだ松平定信の娘・壽子(としこ)が描いた月』を開催中。11月29日(土)13:30〜15:00にミライエ長岡で、ネイチャーセミナー新企画『ミュージアムSalon−コネクト−』未来里山技術機構と里山の未来を考えるトークセッションイベントを開催。








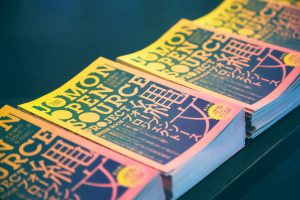












![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)

