この街を出ていく人へ――かつて故郷を捨てた女社長が描く“希望の街”とは・後編

弱冠37歳にして、長岡市で商業プロデュース、事業コンサルティング、起業・ 独立などの支援アドバイスと併せて花屋、レストランなどを運営する合同会社「花越後」を率いる関花代さん。バーを皮切りにフラワーショップ、イタリアンのレストラン、そして焼肉店にも挑戦する意欲的な経営者には、若き日にこの街に居場所を見出せず、逃げるように出て行った過去があった。
「5年でまた街を出る」その決意を胸に戻ってきたという彼女が、その後この街に対して抱いた思いの変化とは。そして、見据え始めた「故郷の街の未来」とは——。
前編はこちら。
「人が育つ場」を見て芽生えた思い
27歳の10月、花代さんは再びこの街に帰ってきた。
そこで見たものは、地方都市の現実。折からの不景気で元気を失いつつあった中心市街地にリーマンショックがとどめを刺し、停滞したムードが漂う街には、自分が働きたいと思えるような店は一つもなかった。きらびやかでエネルギッシュな博多の夜と比べると、何もかもがくすんで見える。
長岡の街に対する辛い気持ちや、やり場のない怒りも、自分の中にはまだ渦巻いていた。「5年やって、福岡に帰ろう。あくまで自分のケジメをつけに帰ってきたのだから」そんな前向きなのか後ろ向きなのかわからない気持ちで、自ら出店することを選んだ。
だが、帰ってきてから最初の夏。開店準備に追われる中、長岡の花火大会を見た。中越地震からの復興を誓う「フェニックス」や戦災復興の象徴となった「白菊」が空に舞うのを眺めながら、ふと「美しいものだなあ」と思っている自分に気づく。
「“5年間だけだから”という言い訳じゃなく、“5年間しかないのだから”という気持ちで、全力でやろう」——この時初めて、一度飛び出した故郷の街とも全力で向き合おうと思ったのだった。
そうして、バー「SAVOY」をオープン。ビルの2Fというわかりづらい場所をあえて選んだ。メニューもフードもない。その代わりに極上の葉巻が吸えて、内装は隅々まで上質さにこだわった、赤と黒の空間。絨毯の毛足の長さにも1ミリたりとも妥協しない、長岡では異例ずくめの店。
「いきなり、博多のスタイルを投入したの。かなり突っ張ってたね、今思うと」そう笑う花代さん。オープンの案内状も、長岡時代のお客さんや友人に60枚ほどしか出していない。しかし、開店日には彼らがたくさんの人を連れてきてくれたのだという。
この街には、確かに自分を気にかけてくれる人がいた。その思いが、花代さんを少しずつ次の動きへと誘ってゆく。


「SAVOY」に新スタッフ・小野さんが加入したのは、開店から2年後。大分出身の小野さんは、長岡にほど近い岩室出身の奥さんと結婚し、もともと花代さんが福岡にいた時の縁でこの店の門を叩いた。
その小野さんに、花代さんは自分が福岡で学んだのと同じく「頭がちぎれるくらい考えること」を徹底して教え込んだ。
「とにかく、何をやらかしても“何故こうなったの? どうしてそう思ったの?”と徹底的に聞かれる。すごく厳しかったです。あまりの辛さに耐えかねて、一度失踪したくらい」と語る小野さんに「失踪って、家の2Fから1Fにでしょ? ものすごく近いじゃない!」と笑いながら突っ込む現在の花代さんからは想像もつかないほど、当時はピリピリしていたのだという。

「歩く姿勢が悪かったから、小野をいきなり日本舞踊のお稽古に放り込んだりしたこともあったなぁ。安易にこちらから答えを示してしまうと、絶対に成長しないからね。そういう思いは当時も今も変わらないんだけど、当時はその言い方や態度もかなりきつかったと思う」
しかし、そんな試練を耐え抜き、小野さんは少しずつ成長してゆく。小野さんにつく新しいお客もちらほらと出始めるのを見守りながら、花代さんの中にある思いが芽生え始めた。
「自分のやりたいことは、もうカウンターの中をはみ出しているんじゃないか」
場所を作り、人を育て、そこに集まってきた人たちがまた新たな関係性や目標を見つけ出してゆくという状況を作り続けてゆくこと。それが、自分の使命なのではないか。そう思ったのだ。
「私はとんがるだけとんがって、そういうものや場所を作る方。小野みたいなのは新しく作るというよりは、それをつないでいける人間。そう思ったから、“世代交代しよう”と言って、小野に店を譲ったんです。なんというか、“あー、ひとり送り出した!”っていう気持ちになりましたね」
県外から移住してきた小野さんが新たにこの街で生きる場所を見つけてゆく過程を見てきた花代さんには、いつしか心境の変化も芽生えていた。「その時には、もう花屋も始めてたからね。5年で福岡に戻るはずが、結局そのまま長岡にいることになっちゃった」
「外を見てきた人」が集まる場所に
そこから、話は冒頭の「リアン」や「カルネ」の開店経緯へと戻って行く。特徴的なのは、「リアン」を切り盛りする清水さんも、「カルネ」のシェフやスタッフたちも、GOOD LUCK COFFEEの青柳さんも含め、花代さんの周りで働く人のほとんどが一度長岡を出た人々か、もしくは県外からの移住者であるということだ。

「それは、やっぱり私が一度外に出てることが関係してると思う。“これがこの街の正解です”みたいなものを押しつけることがないから。
気づいたら、自分よりも何かに特化してる人が周りにたくさんいたのよ。でも、その才能や思いを活かす場所や雰囲気がこの街にはまだ足りない。だから、自分がやっていこうと思った。そういう人たちが働きたいと思える、多様性のある場所や会社ができれば、街が少しずつ“住みたい街”に変わっていくでしょ。次に何かを始める人が増えたり、出て行った人が戻ってきたくなるような街になればいいと思うし。
あと、個人的には、一緒に働く個性豊かな人たちの“その先”に関われる、その人がどうなって行くのかを見ることができるという役得もあるし……もしかしたら、家族の繋がりがないぶん、それを求めているのかも」
そう語りながら、花代さんは次の場所へと向かった。
今はもう「リセットしたい」とは思わない
市内中心部で運営している焼肉店「京城苑」。新潟市内にある老舗店舗との業務提携ということだが、ここも花代さんにとっては「この人たちじゃなきゃ、やらなかった」という“人ありき”のお店だ。
目につくのは、アルバイトに高校生くらいの年の頃の姿が多いことだ。しかも、皆、どこかエキゾチックな顔立ち。中東やアジア系のハーフの少年少女が大半だという。
「別に狙って雇ってるわけでもなく、別のバイトの子づてに紹介されたりして、気づいたらこうなってたんだけどね。親御さんもいろんな事情で日本に来ているし、中にはちょっと家庭が難しい子もいるから、こうやってちょくちょく顔を出してはみんなで話をしたりするようにしてる」
カウンターで酒を傾けながら、アットホームにパートの女性やマスターと談笑する花代さん。社長だからとふんぞり返るようなことは一切しないし、スタッフも自然に受け入れる。日頃から密に接している証だ。
「あの子、今年で高校卒業だよね? お祝い、なに贈ろうかね。ネクタイとか……柄が難しいなあ」この日はシフトに入っていないアルバイトの状況や家庭環境なども含め、かなり細かいところまで把握し、気を配っている様子だ。かつてこの街でよるべない気持ちを味わっていた頃の自分を、彼ら彼女らの中に見ているのだろうか。


「彼らを見ていて“街の寛容さとは?”みたいなことについても考えなくはないけど、私があの子たちと接する時には、そんなことよりとにかく“今を大事にしよう”と思ってる。いつか絶対に別れは来るし、10年後、20年後まで面倒を見られるわけじゃない。とにかく、今、隣を一緒に走ってあげる人がいるといないとでは、大きく違うと思う」
彼らを変に導こうともコントロールしようとするでもなく「本気で伴走する」という姿勢は、どこか、運営している店舗に対する態度とも共通しているように見える。
「餅は餅屋だし、人間はみんな違うからね。『SAVOY』で小野を叱り飛ばしていた頃はもっと、時には必要以上に自分にも他人にも厳しかったと思う。イチかゼロかという気持ちだったのかな。それこそ、かつてこの街で過ごした過去に対して“リセットしてゼロにしたい”と思ってたし。
だけど、少しずついろんなことを積み重ねてきたからこそ、今はもう“リセットしたい”とは思わなくなってきた。寂しさや辛さ、自問自答や求めるものも死ぬまで限りなくあると思うんだけど、少しずつ角が取れて“完璧な調和”みたいな人になれるといいと思う」
この街を出てゆく人へ
そう言いながらも、現在進行中の新しいプランに話が移ると、堰を切ったように勢い込んで語り始める。目を輝かせながら話すその姿は、まだまだ達観のようなものとは程遠い。
「これからも、新しいことをどんどんやっていきたいんだよね。それを通じて、この街がいろんな人にとって居心地のいい場所になるといいと思う。“若者が出て行ってしまう”ってよく言うけど、出て行ってしまうような街になってるのは、はっきり言って、ここにいる大人たちの責任だから。
とはいえ、戻ってきて“郷に入って”みたからこそ、この街特有の事情や、それまで自分が背を向けてきた人たちなりの生き方や孤独もあるということがわかった面もある。だから“みんなが居心地いい”風にできるといいなと思うよ」

誰かの作った“普通”を押しつけられてもがき苦しみ、一度は街を飛び出したからこそ、花代さんは「人生には、あらゆる可能性がある」と語る。
「たとえ夢を持てない環境で育ったとしても、いつか夢を持てる時も来る。それは、私が証明してるから(笑)。だから、もし今何かにやるせなさを感じてる若い人がいたら、その問いに答えが出なくてもいいから、とにかく“なぜだろう”と考えるといいと思う。それが、もしかしたら10年後くらいに突然、自分だけの答えになって現れるかもしれないんだよね。
若い子たちも、別に目的もなくても外に出たっていいと思う。都会に埋もれるのもまた人生だし、ましてや“すぐに帰ってこい”なんて思わない。“普通のこと”なんてないんだから、何を選んでもいいんだよ。
ただ、たまに帰ってきた時に、この街が少し変わっているのを見て“おっ”と思ってもらえるといいと思うな。一度出た人、たまたま訪れた人、ずっと住んでる人でも、誰かがそこに希望を見出せるようなものが作れたらって……誰もやらないなら、私がやり続けるからさ」
この春も、数多くの若者が生まれ育った街を出てゆく。ある者は大きな夢を抱いて、またある者は何もない田舎にうんざりして。それぞれの理由で、街に残るものもいる。
誰も、何も、間違ってなどいない。一度は捨てた故郷を“希望の地”に変えようと走り続ける花代さんの姿は、そんなことを訴えているようにも見える。
Text & Photos : Takafumi Ando
前編はこちら。







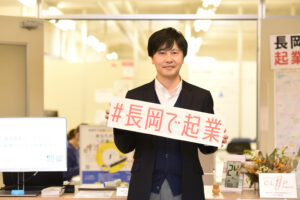












![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)

