暮らしはいつでも旅の途中。まちを体験する古民家ゲストハウス「NEMARU」が提供する「ほんとぐらし」とは?

これぞ米どころ・新潟県!と言いたくなるような一面の水田が広がる越後平野の真ん中に位置する、長岡市与板地域。長岡市中心部からは少し離れているものの、かつて戦国時代の名将・直江兼続が治めた歴史や、刀鍛冶から連なるものづくりの伝統を思わせる、質実さのある街並みが印象的な土地だ。
この地の目抜き通りから一本入った住宅地に、古民家を改装した一軒の宿がある。
「NEMARU ほんとぐらし」という名のこの宿は、いわゆるゲストハウス。ゲストハウスとは、個室で区切られたホテルなどではなく、各地を身軽に旅する旅人たちが時には相部屋に宿泊し、リビングのような共有スペースでくつろぎ、語らいを深めるタイプの宿だ。現在は一棟貸しのみの対応になっているが、いずれにせよ特段観光地やビジネス街というわけでもない場所にこうした宿があるのは、長岡では珍しい光景。食事は外に行ってもいいし、近所で食材を買ってきて自分で料理をしても、バーベキューをしてもいい。さらに特徴的なのは、居間にずらりと並ぶ古書の数々だ。周辺を精力的に歩いてもいいし、本を読みつつ一日じゅうこの居間でゴロゴロしていてもいい。わかりやすくパッケージされたアクティビティなども特にないが、ここで起こることすべてが忘れられない体験になりそうな、そんな不思議な雰囲気のある「NEMARU」。この場所はいかに生まれ、どのような考えで運営されているのだろう。宿の主である三浦大輔さんとかおりさんご夫妻に話を聞いた。
自転車ひとり旅の先に辿りついた
「ゲストハウスをやりたい」という夢

三浦大輔さんは長岡市の生まれ。「蔵王権現」の名でも知られる金峯神社にほど近い場所で生まれ育った。市内の工業高校を卒業後、進学で東京へ出たが、新潟へとUターンすることになる。
「よくある話ですが、地元にはあまりおもしろいことがないと思っていた人間なので、高校を出たらすぐに東京に行こうと思っていたんです。ただ、東京ではコンピューターグラフィックを学んでいたんですが、人の多さが『自分には合わないな』と思って。それで新潟市の専門学校に入り直して、プログラミングを学ぶことにしました」
そんな大輔さんの人生を決定づけたのは、学校の夏休みに出た「自転車ひとり旅」だった。
「夏休みの思い出づくり、という程度のつもりで、新潟から、まず山形県の酒田に行ったんですよ。そのまま海沿いを青森まで北上して、さらに船に乗って北海道に渡って、ずっと北上しているうちに、いろいろな旅人との出会いがあったんです。特に北海道はバイクの一人旅をしている方がとても多くて、衝撃を受けました。
その後、新潟市で新卒で就職し、プログラマーとして三年ほど働いていたんですが、その学生の時の旅が忘れられなくて。お金も少し貯まったかなというタイミングで会社を辞めて、日本一周の旅に出たんです」

学生の時と同じ自転車に乗って選んだのは、北を目指した当時の旅とは逆のコース。新潟県から日本を反時計回りして、沖縄を目指した。
「もう、こうなったら全都道府県を制覇くらいしないと気がすまないぞと思って、日本中を走りました。そして、沖縄で初めてゲストハウスに出会ったんです。その頃は今のようにどこにでもあるというものではありませんでしたから、日本人だけでなく外国の人など、とにかく多彩な人が集まる場所に衝撃を受けました。普通のホテルと違って、冷蔵庫やキッチンを共用しながら自分でご飯を作って食べて、時には仲良くなった人と一緒に外に食べに行ったりと、まるで生活のような旅をして、『こういうものが新潟にもあったらいいんじゃないか?』と思いました。ただ、その時はまだ自分でやるとまでは考えていませんでしたね」
約半年の日本一周を終えて新潟に戻った大輔さんは、再びコンピュータ関連の会社に就職する。シェアハウスに入居しながら勤務していたが、入社後、わずか一年で再びの転機が訪れた。
「会社が潰れてしまって(笑)。それで、『今後どうしようか』なんて考えながら、買ったばかりの車で青森まで旅に出たんです。海沿いを走っていたら途中にイカ焼き屋さんがあったので休憩しようと寄って、お店のおばちゃんに身の上話をしていたんです。『また会社に入ろうかな』なんて言ってたら、おばちゃんに『自分で何かをやり始めないと、何も変わらないよ』と言われてしまって(笑)。そこで、じゃあ自分は何がしたかったんだろう?と振り返ると、やはりゲストハウスというものが自分にとっての衝撃だったので、それをやりたいと思ったんです。
いざやるとなったらやはり勉強が必要なので、今度はバックパックで西日本を巡ることにして。いろいろなところを転々としながら行く先々の宿の方にお話を聞いていたんですが、中でも『ここはいいな』と思ったのが、岡山県の倉敷にある有鄰庵(ゆうりんあん)という宿でした。築100年以上の古民家で、昼はカフェやイベントスペース・夜はゲストハウスという形で地域と溶け合いながら旅人を迎え入れていて。そこがちょうど2店舗めを準備中でまた古民家を改装していたので、そのお手伝いに入りながら宿の勉強をさせてもらったり、ゲストハウスを運営する上で大事なことをいろいろ教えていただきました」
大林宣彦監督『この空の花』で号泣…
「地元でやろう」と決断して与板を選ぶ

転機も学びも旅の中。根っからの旅人である大輔さんは、いよいよ自分の宿を開くことを決意する。その場所に選んだのは、地元・長岡だった。
「あとは、長岡を舞台にした大林宣彦監督の映画『この空の花』を見たのも大きかったです。岡山で働いていたときに尾道に行く機会があって、ちょうど大林監督もいらしての上映があったんですが、冒頭シーンで信濃川にかかる長生橋や土手の映像が出た瞬間に、自分の暮らしていた思い出がバッと頭の中に出てきて、もう最初から涙がボロボロ出たんです。周りは尾道の人ですから『新潟の風景なんだなー』と普通に見ているんですが、私だけ号泣(笑)。あんなふうに泣いたのは人生で初めてで、今でも忘れられないです。その時までは『岡山で宿をやるのもいいな』と思っていたんですが、あの瞬間に『新潟に帰ろう』と。
なかでも最終的に与板にしたのは、自分が自転車で旅をしていたので、そういう人に来てもらいたいと思ったら比較的平坦な土地がよかったことがひとつ。もうひとつは、自分のやりたいことが『新潟を知ってもらう』『新潟に滞在してもらう』ということだったので、やっぱり新潟らしい平野が見渡せる内陸部で、商店や酒蔵もあってまちの歴史が感じられ、加えて自然もすぐそばにあることでした。それらを総合的に見たときに、与板がいいと思ったんです。寺泊の海にそこそこ近いのも好ポイントですし」
運も味方した。与板の名物喫茶店「でくのぼう」の店主が身内の知人だった縁で、現在の平屋を紹介してもらうことができた。そして、何よりも地域住民が最初から暖かく迎え入れてくれたのだ。
「一人でゆっくりやろうと思っていたので、ちょうどいい大きさの建物があってよかったです。住宅街なので観光客が集まるような場所は迷惑がられるかな……と思いつつ近隣の方々にご挨拶をしに行ったら、『もうまちに若者がいないから、どんどん連れてきてよ』なんて言われたりして、歓迎してくださる方ばかりで。いいところだなと思いました。商店街からは少し離れていますが、そこを歩いている人の姿は見える距離ですし、まちの暮らしも垣間見ることができる。『ここにしよう!』と決めて、2016年の3月に入居しました。
しばらく空き家だった物件なので放っておかれた庭木がずいぶん伸び放題になっており、まずはそれを切り拓くところから始めなければなりませんでしたが、やってみたら思った以上にスッキリと風通しのいい場所で。それもラッキーでしたね」
立ち上げにまつわる改装などは機械の力を借りることなく、すべて手作業。しかし、一人では到底追いつかない。ここで大輔さんの旅の経験がさっそく発揮された。
「これまで出会った旅人たちのSNSや、自分のInstagramを活用して、力を貸してくれる人を募りました。毎日この場所の作業状況を更新しながら、旅人たちに『手伝ってくれるなら無料で泊まっていいよ』と呼びかけたりして。自分もそうでしたが、長旅をする人はそういうのが大好物ですから(笑)。おかげで、いろいろな人が手伝ってくれました。
ただ、自分もここに住みながらの作業だったので、リビングに人がたくさん滞在するとなると、ひとりになれる場所がなくなってくる。それで裏に小屋を立てて、自分の生活はそこをベースにしました。あとは前庭にもウッドデッキを作ろうとしているうち、夏頃のオープン予定だったのが、夏が過ぎてしまいまして。もうこれは焦らず、じっくりやればいい……と切り替え、結局2017年の2月1日に開業することになりました。一年弱かかりましたね」

つけた屋号は「長岡ゲストハウスねまる」。「ねまる」とは、長岡弁で「座る」という意味だ。
「人に『ねまってけ〜』みたいな使い方をするんです。ここに寄って、座って落ち着いてもらって、それから土地を知ってもらいたい。そういう思いを込めました」
「盛り上げる」ではなく「入り口」として
まちとの関わり方を考え直した
一人きりで始めたゲストハウスではあったが、SNSでの発信などを通じて少しずつ旅好きのお客さんが来始めた。大輔さん自身もこの場所で生活をしているため、宿泊客とは日常的なコミュニケーションが生まれ、それに心地よさを感じた人はリピーターとなっていく。ちょうど来日観光客を呼び込むため「インバウンド」という言葉が盛んに叫ばれていた頃だが、観光客むけにわざわざパッケージしたようなものではない「生活の香り」とでもいうべきものを求めて、そして他者との交流を求めて、国内外の旅人がここを訪れるようになった。
「築60年ほどの古家ですから給湯器やキッチンもちょっと昔の雰囲気なんですが、若い人はそういうのを珍しがってくれたり、外国の方はそれっぽく作られたものではない日本の生活文化を感じに来てくれたりして、よかったなと思います。壁を白く塗ったりウッドデッキを作ったりといったことはやりましたが、なるべくこの建物や土地に流れてきたこれまでの時間を感じてもらえるようにしたかったので……豪雪地帯なので空き家になると早めに壊されてしまう家も多いですが、ここが残っていてくれてよかったです」

一人旅の人もいれば、仲間たちで泊まる人もいて、時には知らないもの同士が一緒に食事をしたり、会話を楽しむのがゲストハウス。そうした温度のあるコミュニケーションを求める人には、この場所の雰囲気はたまらないだろう。
「もともと生活空間だった場所なので、その雰囲気をなくしてまで違うものにはしたくなかったんです。ゲスト『ハウス』と名乗っている以上、家でありたい。だから、食器類や調理器具なんかもピカピカのものだけではなく、ちょっと生活感のあるものを揃えたりして。すっきりミニマルではないですが、これはこれでまた落ち着く場所として捉えてくれる人がいるので、基本的にはずっとその姿勢で営んでいます。
最初はもっと『まちを盛り上げたい』というふうに考えていたんですよ。ですが、私が勝手にそう考えたところで、『いや、静かに暮らしたいよ』というまちの人もいるわけで。そう考えると、入り口となるこの場所をもっと魅力的にして、その先は来た人に動いてもらうほうがいい。なので、いろいろなお店と協力して、なるべく与板のまちを歩いて、それぞれの冒険をしてもらえるような仕組みを作ろうとしてきました。」
サービスで出すコーヒーは近所の「ナカムラコーヒーロースター」で焙煎している豆を使っている。「中村さんに『なんで与板でやっているんですか?』と聞いたら、『このまちを人が歩いている姿がいいと思ったから』と言われたことが忘れられなくて」と大輔さんは言う。軽食として置いているパンも与板のお店「べっこうや」のもの。そういった近隣店舗を周遊してもらうため、与板の複数店舗で使えるオリジナルのクーポンも用意している。与板のまちとの有機的な関わりを作っておくことで、宿泊客にとってはこの場所がハブになるのだ。
「こういう宿を、しかも住宅地のようなところでやっている以上、一人ですべてをやることは不可能ですから。自分のところの利益だけを囲い込もうとするのではなく、周辺とのつながりを大事にしながら力を借りつつ、一緒にやる、という感覚です。
コーヒー屋さん、パン屋さんに限らず、居酒屋さんなんかも含め、このまちには職人気質の人が多いんですよ。自分で何かを作るとか、自分に必要なものを自分で作るということを大事にしている人が多い。歴史のあるまちでもありますし、何日か滞在して街並みを面白がったりしつつ、ここに暮らして活動している人たちのことを知ってもらいたいんです。私自身が何かを生み出しているわけではないんですが、そういうところにアクセスできる入り口でいたいと思います。さらにちょっと足を伸ばせば寺泊の海や、燕三条なんかにもすぐ行けますからね。そんなふうに、地域をめぐる第一歩になれれば」
かおりさんとの出会いがもたらした
「本」という新たなコミュニケーション
そんな「ねまる」に新たな仲間が加わったのは、新型コロナウイルス感染症が猛威をふるい始めた2020年のこと。それがかおりさんだ。

「長岡に用事があったとかで、一人で泊まりに来たんです。その時はゲストとして一緒にお酒を飲んだりというだけでしたけれど、話をしているうちに絵を描いていたりすることもわかって、おもしろい人だなと思いました。自分はどちらかといえばこの宿のように形のあるものを作るのが好きだったんですが、この人は自分にないものを持っている人だな、と」(大輔さん)
「私はUターンで東京から新潟に戻ってきた組で、県内の会社に勤めていました。そのかたわら、『移動書店』としてイベント出店で新刊と古書を売るということをしていたんです。絵を描くのも好きでしたし、そういう話をして盛り上がった記憶がありますね。楽しかったので、そう時間をおかずにもう一度泊まりに来て。そのときも、まだお客さんでしたけれど」(かおりさん)
その後、大輔さんがかおりさんのところに遊びに行くなど交流が深まり、交際が始まる。かおりさんの存在はパンデミックで宿泊客も激減していた大輔さんの心の支えになっただけでなく、「NEMARU」のあちこちに存在する可愛らしいキャラクターの絵や看板の文字といった、この場所の精神を伝えるデザイン的な要素としてもなくてはならないものになった。

「なんというか、単純にすごく平和な絵を描く人だと思ったんです。第一印象も『こんな絵を描く人は、そんな悪い人じゃないだろう』と(笑)。自分ではこの場所でそういう平和な雰囲気を作ろうと思っても、具体的なイメージとしてそれをプラスすることはできないので、偶然の出会いではありましたが、ものすごくしっくりきたんです。とはいえ、『NEMARU』に大きく関わってもらうというようなことはあまり考えていなかったんですが……」(大輔さん)
当時は旅行者だけでなく、かおりさんが移動書店を出していたようなイベントも軒並み中止になっていた。そこに、大輔さんが「だったら、宿の一角に本棚を置いてみる?」と提案。もともと行っていた移動本屋の活動の屋号『古本いと本(いとぽん)』として、最初は本棚を設置するところから、現在の古書店営業まで含む「泊まれる本屋」としての形が、少しずつ動き出した。
「もともと私の漫画本は置いてあって、お客さんも読めるようにしていたんですが、ここに本を置いたらまた違うことが起こるだろうなと思ったんです。旅にまつわる本や雑誌を置くのも、もちろんいいし。いずれにせよコロナ禍であまり自由に動けない時期でしたから、この場所を訪れた人たちがじっくりとここで時間を使ってもらいたかった。その時間に、本というものがとてもマッチするのではないかと。
本って、単独で存在していてもいいですけど、コミュニケーションの媒介になれるものですよね。人と人との間にあればその本をきっかけとして会話が生まれるし、一人で読んでいても、自分の知らない世界との対話のようなものになり得る。それはある意味、旅と同じことだと思いますから」(大輔さん)
「宿としての作業には、実質的に私はほとんど関わっていないんですよ。ただ、本棚として関わると、例えばお客さんが泊まって帰られたあとに蔵書がちょっと動いていたとか、そんなことから『ああ、あの人はこういう本が気になったんだな』ということを思ったり、もちろん気に入って買って帰っていただくことも含め、出会いを演出できるのは楽しいなと、改めて思いました」(かおりさん)

コロナ禍で多くの人が感じた
「ほんとぐらし」の大切さ
だが、その一方でパンデミックの影響は非常に大きく、一時は県外客がほぼ途絶えた。経営面では苦闘を強いられる日々が続くが、そんな中でも次なる芽は少しずつ育っていた。他の地域から来る人と同じ空間に滞在することに不安を覚える宿泊客もいることを考え、ひとグループ単位での一棟貸しにしたことで、それが明らかになる。
「県内のお客さんたちが『こんなところがあったんだ』と知ってくれて、リピーターとして何度も来てくださるようになって。とてもありがたかったです。旅人というわけでもなく、例えばママ友同士で泊まったり、同級生同士だったり、お盆に帰省はしたけれど感染リスクも考えて実家には泊まらないことにした人たちとか。『こういうゲストハウスの使い方もあるんだ!』という思いでした」(かおりさん)
「そういうお客さんたちのおかげで、なんとか乗り切りましたね。暇なときのほうが多かったので、ものすごく釣りに行きましたけど(笑)。海も近いし、ほぼ毎朝ね」(大輔さん)
大輔さんの守り続けてきた「生活の場である」ことの美学が、親密なもの同士で安心しあって過ごせる空間を求める心にマッチしたということだろう。この頃から、当初「長岡ゲストハウスねまる」だった宿の名前は「NEMARU ほんとぐらし」に変わった。

「“本当の暮らし”と“本との暮らし”、両方がかかっているんですが、第一には与板のリアルな暮らしを体験してもらい、土地を知ってもらうということ。料理も地場のお店に買いに行って自分で作って、地元の人と同じ暮らしを体験してもらいたいということです。もちろん、何が“本当”なのかといったことを軽々しく決めつけるわけにはいきませんが、少なくとも作りものではないもの、というか。ここでの暮らしが、その人の中での“本当”を見つけるきっかけになればいいと思います。そうした、一人ひとりの経験そのものが“本当の暮らし”であり、“本当の旅”でもありますから」(大輔さん)
そして、“本当の暮らし”はここを営む大輔さんとかおりさん夫妻自身の日々の暮らしのことでもある。日々生きて暮らしている人間が営んでいる場所である以上、 “本当”がずっと同じもののままではあり得ないのも魅力的なところだ。
「無理に新しいものとか流行りのやり方を取り入れたいとは思わないんですが、自分の理想の形みたいなものをちょっとずつ磨いていくということは続けたいんです。なんだか、完成させてしまうとそこで止まってしまう気がするので、常に手を入れて、常に『一番新しい状態』でいたいと思っています。庭にアウトドアっぽく楽しめるエリアを作ってバーベキューをできるようにしたり、プロジェクターをつけたり、といったマイナーアップデートを続けています。小さなことかもしれませんが、いつも最新の状態である。そういうふうに思いながらやっていきたいですね」(大輔さん)

「この場所イコール私」と言い切る大輔さん。自分自身の中で考えや好み、または単に気分が変わっていくのをそのまま自分の場所に反映することができるというのは、実は最も贅沢なことなのかもしれない。
「たくさんの宿に泊まってきましたが、本当に、宿は人そのものだと思います。ゲストハウスも今では乱立していますが、オーナーさんがきちんとその場所の顔として働いているところは、どこもすごく温かかったなと思います。私はそういうタイプの宿が好きだったので、『NEMARU』はずっと私の手で続けていきたいです。
とはいえ、もしもスタッフを雇える余裕ができたとしたら、もっと新しいことを大きくやりたいなとは思っているんですよ。今日これから初めて『NEMARU』に泊まりに来るお客さんがいるんですが、長岡駅からバスに乗ってわざわざ来てくれるそうなんです。途中は田んぼだらけになる道を走りながら『本当にこの先に行っていいんだろうか?』という不安を抱いて来られるかもしれませんが(笑)、その先にあるのがこの場所だったことで安心してもらえるといいですね。そんな場所を作るためには『私だけの場所』のままでもいけないので、いずれは人を入れたいんです。企画とか広報といったことをお手伝いしてくれる人がいれば、私は宿の運営や、お客さんとのやり取りにもっと注力できますから」(大輔さん)
あとに続く人のため、家族のため
「ここにいる」という冒険は続く

与板という、長岡の中心部からは少し外れた場所にあってもこういうことができるのだから「新潟なら、どこでだって成立するはず」と、大輔さんは語る。
「ここに泊まりに来られたお客さんで『新潟に住みたいと思ってるんです』と言うので私がまちを案内して、最終的には家を借りてリノベーションして住むことになった方もいます。結局のところ、まちは人で変わりますし、与板くらいの規模のまちなら、一人入ればものすごい変化を生む可能性もある。私の今があるのも、青森のイカ焼き屋のおばちゃんと、大林監督の映画『この空の花』に出会ったからといっても過言ではありません。そんなふうに、人や、人が思いを込めて作ったものに出会うことによって人生が変わることは確かにありますから、私がやっていることも誰かのきっかけになるといいなと思います。
決して器用とはいえない自分が手をかけてこれくらいにはなっているんだから、他のみんなも、もっと自分のやりたいことを試せるんじゃないかな。あとに続く人の中に、『中心部でやらなくてもいいんだ』という冒険心が生まれてくれると嬉しいです」(大輔さん)
地元に場所を構え、長男の陸人くんも誕生。まちにすっかり根をおろしたように見える自分自身の今をどう捉えているのだろうか——最後にそう問うと、「さすがに、自分自身が旅に出ることは少なくなってしまいました。ちょっと旅人勘が鈍っている気もするので、ひさしぶりに一人旅にでも行きたいですね」「え〜、私も一人で行きたい」とご夫妻で笑いながら、まっすぐにこう答えてくれた。

「私自身がそうでしたけれど、与板や、新潟の外から来た人と県内や町内の人が出会って、もっと関わりができるような場所になっていけば、すごくおもしろくなると思うんです。私もお客としてきていたときは、常連さんとお話しするのがとても楽しかったですし。そういうことを本を通じてやれるといいですね。宿泊のお客さんでなくても買える古書店としてまちにひらくということも、いずれはやってみたい。読書会をやったり、選書を充実させたりしつつ、自分自身ももっと外の世界を見て、この場所をもっとよくできるようにしていきたいと思います」(かおりさん)
「自分では自転車旅という冒険をずっとしてきましたけど、それはもう終わったと思っていて。今は子どもがいるので、家族に背中を見せられるようにこの場所をしっかりと守っていきたいんです。彼が大きくなったら一緒にやってみたいこともたくさんあるし、私の真似をするのではなく、私を超えて行ってもらいたいという気持ちもありますね。
とはいえ、さっき言ったように、今の形だけで終わらず、もっと大きくしていきたいという欲もある。いろいろな出会いもこれからあるでしょうし、まだまだどんな楽しいことがあるかわかりませんから……冒険は終わったなんて言いましたが、今もまだ途中なんですね、やっぱり」(大輔さん)
日々の「ほんとぐらし」を重ねながら作り上げる、ほんの少しだけ先の、人とまちと生活の姿。三浦さん夫妻は今、そこに向かってそれぞれの旅を続けているのかもしれない。忙しい日々の中で自分自身の暮らしを見失いそうになったら、あらかじめ仕入れた情報を確認しに行くだけのような旅に飽きたら、予定や目的などなくても「NEMARU」の扉を叩いてみてはいかがだろうか。

Text:安東嵩史 / Photo:八木あゆみ(ともに「な!ナガオカ」編集部)











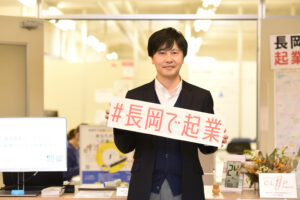










![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)

