
#ものづくり
記事一覧
-
 2024/02/16
2024/02/16季節限定の和菓子から「猫神さま」まで。長岡の風土と文化に息づくニャンコたちの姿を求めて
まちと記憶 | ものづくり | 気になるスポット | 犬猫好き必見
-
 2023/08/04
2023/08/04まるで秘密基地!長岡・栃尾にひっそりと佇むツリーハウスに日本屈指のビルダーを訪ねた
アート・デザイン | どう生きる? | ものづくり | やばい技術 | 中山間エリア | 気になるスポット
-
 2023/05/17
2023/05/17中山間地に移住して15年。震災復興に伴走したハンドメイド作家・わきたたえこさんの「地域に生きる」手仕事
コミュニティ | どう生きる? | ものづくり | 中山間エリア | 移住・UIターン | 趣味が高じた人
-
 2023/04/03
2023/04/03価値を「+1」するものづくりで地方から世界的ブランドに。 挑戦を続けるオンヨネの企業哲学
ふるさと納税 | ものづくり | やばい技術 | 産業エリア | 長岡で働く
-
 2023/02/10
2023/02/10自然な流れに身を委ね、自由に境界を越える。陶芸作家・矢尾板克則さんの“ズレてる”生き方
アート・デザイン | ものづくり
-
 2022/12/02
2022/12/02世界シェアNo.1の品質、誰もが働きやすい制度設計。進化を続ける100年企業・鈴民精密工業所
ものづくり | やばい技術 | 産業エリア | 長岡から世界へ | 長岡で働く
-
 2022/04/04
2022/04/04「地域と歩む障害支援」とは何か。アート制作販売から広がる「工房こしじ」の共生の輪
アート・デザイン | イベントレポート | タウンエリア | ものづくり | 産業エリア | 田園エリア | 長岡の福祉
-
 2021/10/21
2021/10/21ワイン造りはまちづくり。長岡・栃尾産日本ワイン「T100K」の先にある「まちの未来像」
ものづくり | 中山間エリア | 発酵・醸造 | 移住・UIターン
-
 2021/10/04
2021/10/04スピードメーターの名門「日本精機」の新製品は…CO₂測定器!? 変わる時代と、変わらぬ技術への誇りを聞いた
おもしろい会社 | コロナ禍と長岡 | ものづくり | やばい技術 | 産業エリア | 長岡で働く
-
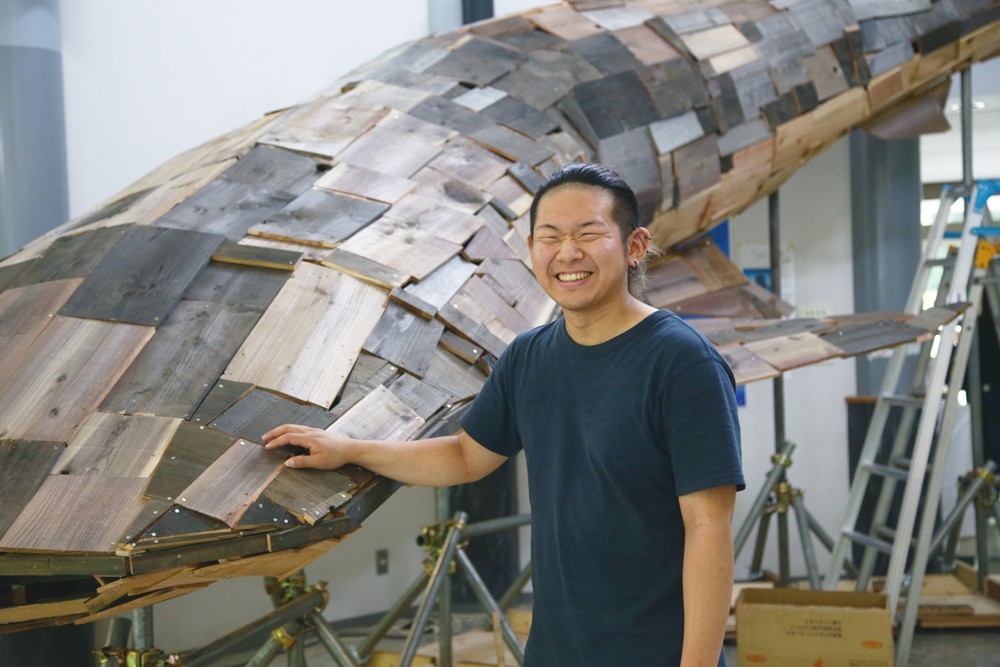 2021/09/17
2021/09/17長岡・栃尾に現れた「木の魚が泳ぐ」水族館。人の縁が命を吹き込む加治聖哉さんの廃材アート
アート・デザイン | どう生きる? | ものづくり | 中山間エリア | 移住・UIターン | 長岡造形大学












![http://[総合メニュー]イベント情報集約サイト5-3](https://na-nagaoka.jp/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/総合メニューイベント情報集約サイト5-3.jpg)

